「絵の具って、これ何ゴミなの?」そんな疑問を持ったこと、ありませんか?
この記事では、絵の具の種類別の分別方法から、正しい捨て方、素材ごとの処分ルール、子ども用セットの扱い方まで詳しく解説します。
「まだ使えるけど、どうしよう?」という人向けに再利用アイデアも紹介していますので、絵の具を無駄なく手放すヒントが見つかりますよ。
ぜひ最後まで読んで、絵の具をスッキリ処分できる未来を手に入れてくださいね。
絵の具は何ゴミか徹底解説

絵の具は何ゴミか徹底解説します。
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
水彩絵の具は基本的に可燃ゴミ
まず、水彩絵の具についてです。
一般的に、学校や家庭でよく使われる水彩絵の具は「可燃ゴミ」に分類されます。
チューブもプラスチック製のものが多いため、自治体のルールに従えばそのまま可燃ゴミとして処分可能です。
ただし、チューブの中にまだ中身が残っている場合は、その絵の具が乾いてから捨てるようにしてください。
液体状のままだと可燃ゴミに出せない場合もあるので、乾かして固めるのが無難ですよ~。
アクリル絵の具の扱いも可燃ゴミでOK
アクリル絵の具も、多くの自治体では「可燃ゴミ」に分類されています。
水彩絵の具と同じように、使い切ってから処分するのが基本です。
アクリル絵の具は乾くと固まる性質があるので、キャップを開けてしばらく放置すれば中身を固めることができます。
固まった絵の具チューブは、プラスチック製であればそのまま可燃ゴミへ。
処分の手間を減らしたいなら、使い切ってからまとめて捨てるのが楽ちんですね。
油絵の具は自治体に確認を
油絵の具はちょっと扱いが特殊です。
中には有機溶剤が含まれているものもあり、揮発性が高くて危険ゴミ扱いになる可能性があります。
基本的には「少量であれば可燃ゴミ」として処分できる自治体もありますが、安全を考えると、事前に役所や清掃センターに確認するのがベストです。
また、古くなった油絵の具をたくさん処分したいときは、産業廃棄物として扱われるケースもあるので要注意。
とくに美大生や趣味で大量に使っている方は気をつけてくださいね~!
スプレータイプや溶剤は危険ゴミになることも
絵の具の中には、スプレー缶タイプのものや溶剤タイプもありますよね。
これらは「スプレー缶」や「有害ゴミ」「危険ゴミ」として、可燃ゴミとは別扱いになることがほとんどです。
中身を完全に使い切った上で、穴を開けてから指定日に出す、というルールが多いです。
自治体によっては「資源ごみの日に出す」「金属ゴミとして扱う」といった違いもあるので、事前の確認がとても大切。
事故の原因にもなりやすいので、ちゃんと処分ルールは守りましょうね!
中身が残っているとルールが変わる
ここで大事なのが、中身の有無によってゴミの分別が変わること。
たとえば、乾いて固まった絵の具チューブなら可燃ゴミとして出せますが、中身がドロドロのままだと処分不可な場合も。
理由は、液体状のままだと収集・処理のときにトラブルになりやすいからなんですね。
乾かす、固める、新聞紙に包むなど、安全に出せるようにちょっと工夫するだけでスムーズに処分できますよ。
ひと手間かかりますが、そのぶん安心して捨てられるのでやっておきましょう~!
絵の具の捨て方5ステップ
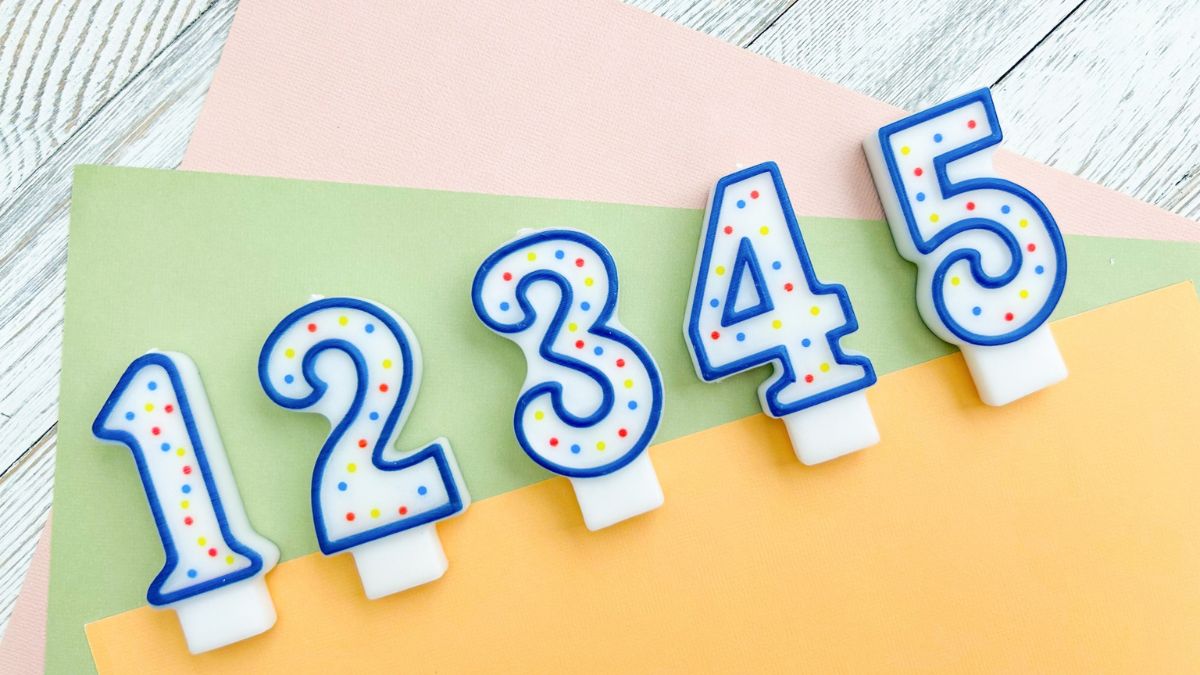
絵の具の捨て方5ステップを紹介します。
順番に実践していけば、どの自治体でも安心して絵の具を処分できますよ~。
①中身を使い切る
まず最初にやるべきは「中身を使い切る」ことです。
当たり前のようですが、意外と中途半端に残ったまま放置している絵の具って多いですよね。
使い切れば、基本的にはチューブもゴミとして出しやすくなるので、とってもスムーズ。
「もう使わないけど、まだ中身がある…」という場合は、紙に出して乾かすのもアリ。
無駄にせずに処分できるので、ぜひやってみてくださいね。
②チューブのフタを外す
次に、チューブのフタを外します。
これは自治体によって「異素材は外して分別する」というルールがあるためです。
たとえば、チューブ本体がプラスチックでフタが金属の場合、分けないと不燃ゴミ扱いになってしまうことも。
「そのまま出していい」としている自治体もありますが、念のため分けたほうが安心。
ちょっと面倒でも、この一手間が分別の正確さにつながりますよ~!
③中身が残っていたら乾かす
まだ中に絵の具が残っていたら、そのまま捨てるのはNGな場合が多いです。
その理由は、液体や半固形のままだと、ゴミ収集時に漏れたり、処理場でのトラブルになったりするから。
中身を紙やパレットに出して、自然乾燥させましょう。
特にアクリル絵の具や水彩絵の具は、乾けば完全に固まるので可燃ゴミとして問題なく処分できます。
屋外の日陰や風通しのいい場所に置くと、早く乾きますよ!
④乾いたら自治体指定の袋に入れる
中身を乾かし終えたら、いよいよゴミ袋に入れていきます。
ここで気をつけたいのが、地域によって「可燃」「不燃」の分類が違う点。
たとえば、アルミのチューブは「不燃ゴミ」になることもあるので、ラベルの素材や本体の質感もチェックしておきましょう。
できれば、分別を明確にするために、紙にメモを添えておくと回収員さんも助かります。
ちょっとした気遣いが、ゴミ出しトラブルを防ぐポイントになりますよ!
⑤分別ルールを再確認する
最後に必ずやってほしいのが、「自治体の公式サイトなどで分別ルールを確認する」ことです。
同じ都道府県内でも、市区町村によってゴミの分別方法は異なります。
公式サイトや配布されている「ごみ分別一覧表」をチェックして、最新の情報を確認してくださいね。
とくに油絵の具や特殊な画材を使っている人は、処分方法が異なる可能性が高いです。
迷ったら、役所や清掃センターに電話で問い合わせるのが一番安心ですよ~。
絵の具チューブの素材別ゴミ分類

絵の具チューブの素材別ゴミ分類について詳しく解説します。
素材によってゴミの分別ルールが変わってくるので、ここでしっかり確認しておきましょう。
プラスチック製は可燃ゴミ
まず、最も一般的な絵の具チューブはプラスチック製のものです。
このタイプのチューブは、基本的に「可燃ゴミ」として処分できます。
ただし、中身が残っている場合は前の章で説明したように、しっかり乾かしてから処分しましょう。
ふた部分が金属になっている場合は取り外す必要がありますが、全体がプラ素材ならそのままでOKなことも多いです。
見た目ではわかりづらい素材もあるので、ラベルの表記などもチェックしてくださいね。
アルミ・金属製は不燃ゴミ
絵の具の中には、アルミ製や金属製のチューブもあります。
こちらは、基本的に「不燃ゴミ」として扱われるケースが多いです。
特に油絵の具やプロ仕様の製品に多く見られる素材ですね。
アルミはリサイクル可能な資源ですが、絵の具が付着していると資源ゴミにできないこともあります。
しっかり使い切り、可能であれば洗って乾かしてから処分すると、より丁寧な対応になります。
紙箱や外装は資源ごみ
絵の具セットに付属している紙箱や、外装パッケージも忘れずに分別しましょう。
多くの場合、これらは「資源ごみ」になります。
汚れていない紙素材はリサイクルの対象になるので、きれいな状態で出すことが大事です。
油や絵の具で汚れている場合は、自治体によっては可燃ゴミ扱いになることもあるので注意が必要です。
「きれいなら資源」「汚れていたら可燃」と覚えておくとスムーズですよ!
パレットは汚れの度合いで分かれる
パレットも捨てるタイミングが来たら、素材と汚れ具合をチェックしてから分別しましょう。
プラスチック製のパレットは、汚れがひどい場合「可燃ゴミ」として出されることが多いです。
逆に、きれいに洗えば「プラスチック資源ごみ」として回収される自治体もあります。
木製パレットは可燃、ガラス製なら不燃など、素材ごとにゴミ区分が異なるため要注意。
「これ何ゴミだろう?」と迷ったら、役所や自治体のアプリなどで調べると便利ですよ~!
子ども用絵の具セットの処分方法

子ども用絵の具セットの処分方法を解説します。
子ども用の絵の具セットって、色々な素材が組み合わさっているので、分別がちょっとややこしいですよね。
筆やパレットの処分方法
筆やパレットは素材によって分別方法が変わってきます。
筆は、木製の柄とナイロン製の毛が多いため「可燃ゴミ」で処分できることがほとんどです。
金属の留め具が付いている場合は、不燃ゴミ扱いになることもあるので、地域ルールを確認しましょう。
パレットについては、前の章でも触れたようにプラスチック製であれば汚れ具合に応じて「可燃」または「プラスチック資源ごみ」です。
いずれも洗えるものはなるべく洗って、きれいにしてから処分すると安心ですよ~!
洗い桶や水入れ容器は何ゴミ?
水入れやバケツ型の容器は、ほとんどがプラスチック製です。
そのため、多くの自治体では「プラスチックごみ」または「可燃ゴミ」として出せます。
しかし、大きさや形状によって「粗大ゴミ」になることもあるので注意が必要です。
割れていたり、変形していたりする場合は可燃ゴミの対象になります。
容器として再利用できそうなら、家庭内での使い道を探すのもいいかもしれませんね♪
絵の具バッグは布製か合成かで違う
学校でよく使う絵の具バッグは、布製や合成皮革のものが多いです。
布製バッグは「可燃ゴミ」で処分できる自治体が大半です。
合成皮革(ビニール素材)の場合は、自治体によっては「可燃ゴミ」か「不燃ゴミ」か異なる判断になります。
中に金属パーツがある場合は、それを取り外して分別するのが基本です。
汚れがひどくなければ、フリマやリユースに回すという手もありますよ~!
セットでまとめて処分しない
最後に大事なのが「全部まとめて捨てるのはNG」という点です。
子ども用の絵の具セットって、バッグの中に筆、絵の具、パレット、水入れ…といろんな素材のものが一緒に入っていますよね。
これを一括で「燃えるゴミ!」と処分してしまうと、回収されない可能性が高いです。
少し面倒ですが、それぞれ素材ごとに分けて、ゴミの種類をしっかり見極めて捨てるようにしましょう。
子どもにも分別の大切さを教える良い機会になるかもしれませんね♪
処分せずに再利用する方法もある

処分せずに再利用する方法もあるんです。
ゴミとして捨てる前に、ちょっと待ってください。
まだ使える絵の具や道具は、別の形で活かす方法もたくさんありますよ!
リサイクルショップに持ち込む
まず、手軽な方法として「リサイクルショップ」への持ち込みがあります。
使いかけでも状態がよければ、引き取ってもらえる可能性があります。
特に子ども用の絵の具セットや画材道具は、需要もそれなりにあるので試してみる価値アリです。
お店によっては未使用品に限るところもあるので、事前に電話やサイトで確認してから持ち込むと安心です。
引き取ってもらえれば、環境にもお財布にもやさしいですよね~!
フリマアプリで譲る
メルカリやラクマといったフリマアプリを活用すれば、使いかけの絵の具でも欲しい人に届けることができます。
「子どもの自由研究に使いたい」「絵の練習用に使いたい」など、意外とニーズがあるんです。
セットで売るのも良いですが、パーツごとに分けて販売すると売れやすくなります。
写真をきれいに撮って、簡単な説明をつければOK。
捨てるくらいなら、誰かに使ってもらえた方が気持ちも嬉しいですよね!
児童施設や学校に寄付する
福祉施設や児童館、小学校などでは、画材の寄付を受け付けていることもあります。
「買うと高いけど、すぐに消耗するからありがたい」と感謝されることも少なくありません。
特に未使用またはきれいな状態のものは、寄付先から歓迎される可能性が高いです。
事前に連絡して確認してから送るようにしましょう。
捨てるより、誰かの役に立つ形で手放せるのって素敵ですよね~!
絵の具を使ったDIYで再活用
最後に紹介するのは、「自分で再利用する」アイデアです。
使いかけの絵の具を使って、ポストカードを作ったり、古い家具に色を塗ってリメイクしたり。
アイデア次第で新しいアート作品や実用品に変身させることができます。
子どもと一緒に「絵の具で遊ぼうデー」なんてイベントにしても楽しそうですね!
創作することで思い出にもなりますし、環境にもやさしい選択ですよ♪
まとめ|絵の具 何ゴミか迷ったらこれで解決!
| 絵の具の種類別ごみ分類 |
|---|
| 水彩絵の具は基本的に可燃ゴミ |
| アクリル絵の具の扱いも可燃ゴミでOK |
| 油絵の具は自治体に確認を |
| スプレータイプや溶剤は危険ゴミになることも |
| 中身が残っているとルールが変わる |
絵の具は一見するとどれも同じように見えますが、実は種類や状態によって処分方法が大きく異なります。
水彩・アクリルは基本的に可燃ゴミでOKですが、油絵の具やスプレー系は注意が必要です。
一番大事なのは「中身をしっかり使い切ること」、そして「素材ごとにしっかり分けること」です。
さらに、再利用のアイデアを活用すれば、ただ捨てるだけでなく、新たな価値も生まれます。
迷ったときは自治体の公式情報を確認するのが一番確実。安全・安心な処分を心がけてくださいね。
▼ごみの分別についての詳細は、各自治体の公式ページなどもご参考にどうぞ。
