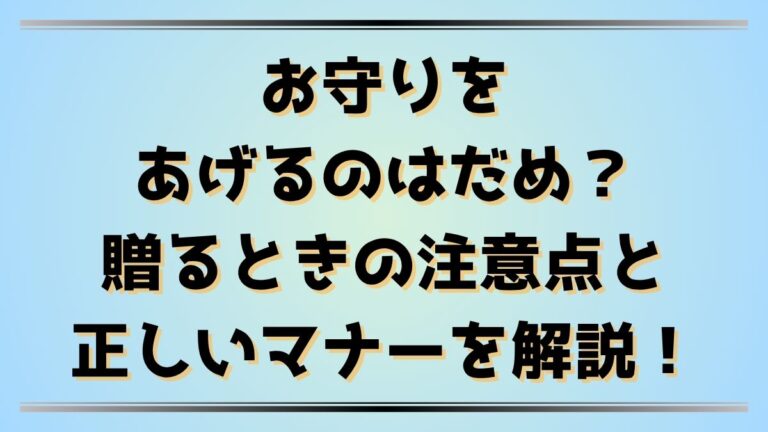お守りを人にあげるのは本当にだめなのか、気になったことはありませんか。
お守りの意味やマナー、タブー、実際に起こりやすいトラブルまで、詳しくわかりやすくまとめました。
善意で贈ったつもりでも、相手を困らせてしまったり、誤解やトラブルになることも。
お守りをあげたいとき、もらったとき、どう対応すればいいのか悩んでいる方に向けて、具体的な対処法や気をつけたいポイントを紹介しています。
この記事を読めば、安心してお守りを贈ったり受け取ったりできるヒントがきっと見つかります。
ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
お守りをあげるのはだめなのか徹底解説

お守りをあげるのはだめなのか、詳しく解説していきます。
お守りを人にあげることについて、疑問や不安を持っている方は意外と多いものです。
例えば、「縁起が悪いって本当?」「マナー違反にならない?」など、周りの人との関係性や常識も気になりますよね。
結論から言うと、お守りは本来「自分のために授かったもの」なので、基本的には自分の身を守るものとして大切にするのが一般的です。
ただ、家族や友人の健康や幸せを願って「お守りを贈りたい」と思う気持ちも素敵なもの。
一方で、何も考えずにあげてしまうと相手を困らせてしまうこともあります。
ここからは、お守りをあげてはいけない理由や、逆に大丈夫な場合、渡すときのマナーや注意点、そして受け取る側の気をつけたいポイントまで、わかりやすく解説していきます。
お守りをあげてはいけない理由
お守りを人にあげるのはよくないと言われる大きな理由は、「ご利益が持ち主にとどまるものだから」という考え方があるからです。
多くの神社やお寺では、参拝者一人ひとりの願いに合わせて祈願したお守りを渡しています。
そのため、お守りは「自分自身のため」に授かるものという意味合いが強いです。
人からもらったお守りは、気持ちはありがたくても「他人の厄や運気まで一緒にもらう」と考える人も少なくありません。
日本の伝統や風習の中では、こうした「お守りの譲渡」に慎重な意見が多いのが現実です。
また、お守りをあげることで「不幸を押し付けている」「責任をなすりつけている」と感じる人もいます。
とくに年配の方や、信仰心が強い方の場合は、こうしたことに敏感なので注意が必要です。
相手の価値観や宗教観を無視してしまうと、思わぬトラブルになることもあるので気をつけましょう。
「善意」のつもりで渡したものでも、相手によっては戸惑わせてしまうことも多いです。
贈り物としてお守りを選ぶときは、相手の受け止め方や気持ちに配慮することが大切です。
お守りをあげても良い場合
お守りをあげても大丈夫なケースもあります。
たとえば、旅行のお土産として現地の限定お守りを買って帰る場合や、合格祈願・安産祈願など特別な願いを込めて贈る場合です。
こうしたケースでは「相手の幸せを願う」という気持ちが伝わりやすく、受け取る側もポジティブに受け入れやすいでしょう。
ただし、「未使用で新品のお守り」であることが前提です。
一度自分で使った(持ち歩いた)お守りを人にあげるのはNGとされています。
また、相手が信仰やお守りそのものを気にするタイプではない場合や、本人から「ほしい」と言われた場合も問題ありません。
最近では、推し活グッズとしてキャラクターのお守りを交換したり、親しい友人同士で気軽に贈り合うことも増えています。
ただし、形式的なマナーよりも「相手がどう感じるか」を第一に考えてください。
お守りを渡すときの注意点
お守りを人にあげるときは、いくつか気をつけたいポイントがあります。
まず、「新品のお守りを、直接神社やお寺で受け取った状態で」渡すこと。
袋から出したり、使いかけのものをあげるのは避けてください。
また、「これはあなたのために選びました」「お守りの由来や意味」などを一言添えると、相手も安心しやすいです。
お守りを贈るときはタイミングも大切で、受験や就職、出産など、人生の節目のタイミングが良いでしょう。
「重荷にならないように」や「お返しは不要です」などの気遣いの言葉も添えてください。
相手が宗教や縁起を気にするタイプなら、「断っても大丈夫だからね」と伝えるのもマナーです。
ちょっとした一言や、細やかな気配りが大切なんですよ。
お守りをもらう側のマナー
お守りをもらう側にも、気をつけたいマナーがあります。
まず、善意で贈られたものは、素直に「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えましょう。
宗教的な理由や自分の価値観で受け取りたくない場合も、やんわりと気持ちを伝えるのがベターです。
無理に受け取る必要はありませんが、断るときは「気持ちだけ受け取ります」や「実家の宗教の関係で…」など、丁寧な言葉を使うと角が立ちません。
もし受け取った場合は、バッグやポーチなど清潔な場所に入れて持ち歩くか、自宅で大切に保管しましょう。
「しばらく持ったあと神社やお寺に返す」なども一般的な方法です。
お守りの扱いに迷ったら、贈ってくれた人や神社に相談するのもおすすめです。
お守りをあげる行為がタブーとされる背景

お守りをあげる行為がなぜタブーとされるのか、その背景について詳しく解説します。
お守りは古くから日本の文化に根付いていますが、「人にあげるのはだめ」と言われる理由には、ちゃんとした背景があります。
一般的な贈り物と違い、お守りは信仰や神仏の加護に深く関わるものです。
知らずに渡してしまうと相手に不快な思いをさせたり、場合によってはトラブルになることもあるので、タブーの理由を知っておくのは大切です。
ここでは宗教的な側面やご利益の考え方、お守りのそもそもの意味について見ていきます。
この背景を知ることで、より適切にお守りと向き合うことができます。
宗教的な理由
日本では神道や仏教など、複数の宗教観が生活に根付いています。
お守りは、神社やお寺で神仏に祈願して授かるものなので、宗教的な意味合いが強いアイテムです。
「自分の願いを込めて神様や仏様にお願いする」ために手元に置くものなので、簡単に人に譲ってしまうのは不適切と考えられています。
また、宗教ごとにお守りの考え方や取り扱いも異なります。
家ごとに信仰している宗教が違う場合もあるので、意図せず相手の宗教的な価値観を傷つけてしまうことも。
とくにお正月や七五三など、人生の節目の行事で授かったお守りは、家族の中だけで大切にするという考えが根強いです。
そのため、お守りをあげるのは「信仰の領域を超えてしまう」と考える方も多いです。
自分と相手の宗教観を尊重する気持ちが大切です。
ご利益が薄れると言われる理由
お守りには「持つ人のためにご利益がある」という信仰が根付いています。
そのため、一度誰かが持ったお守りを人にあげてしまうと、「ご利益が本来の持ち主から離れてしまう」と考えられてきました。
お守りのご利益は、持ち主が願ったことや祈った気持ちと一緒に働くものです。
人にあげることで「気持ちが移る」「ご利益が分散してしまう」といったことが起こると信じる人も多いです。
また、神社やお寺でも「お守りは自分のために持つもの」と説明しているところが多いです。
このような理由から、基本的にお守りの譲渡は良くないと考えられています。
たとえ善意であっても、ご利益に対する考え方は人それぞれなので、慎重になる必要があります。
お守り本来の意味
お守りはもともと「自分や家族を守る」ためのものです。
神社やお寺でいただくお守りには、それぞれ役割や意味があります。
たとえば、健康・安全・学業成就・厄除けなど、願いごとに合わせて授かるものです。
こうしたお守りは、本人が願いを込めて持ち歩いたり、身につけることで、気持ちを強く持つ意味もあります。
この「自分のための願掛け」という部分が、お守りの大きな意味です。
誰かのためにお守りを選んで渡す場合でも、本来の意味や目的を忘れないことが大切です。
お守りの本来の役割を意識することで、贈る側も受け取る側も、より納得して行動できるようになります。
お守りをどうしてもあげたいときの対処法
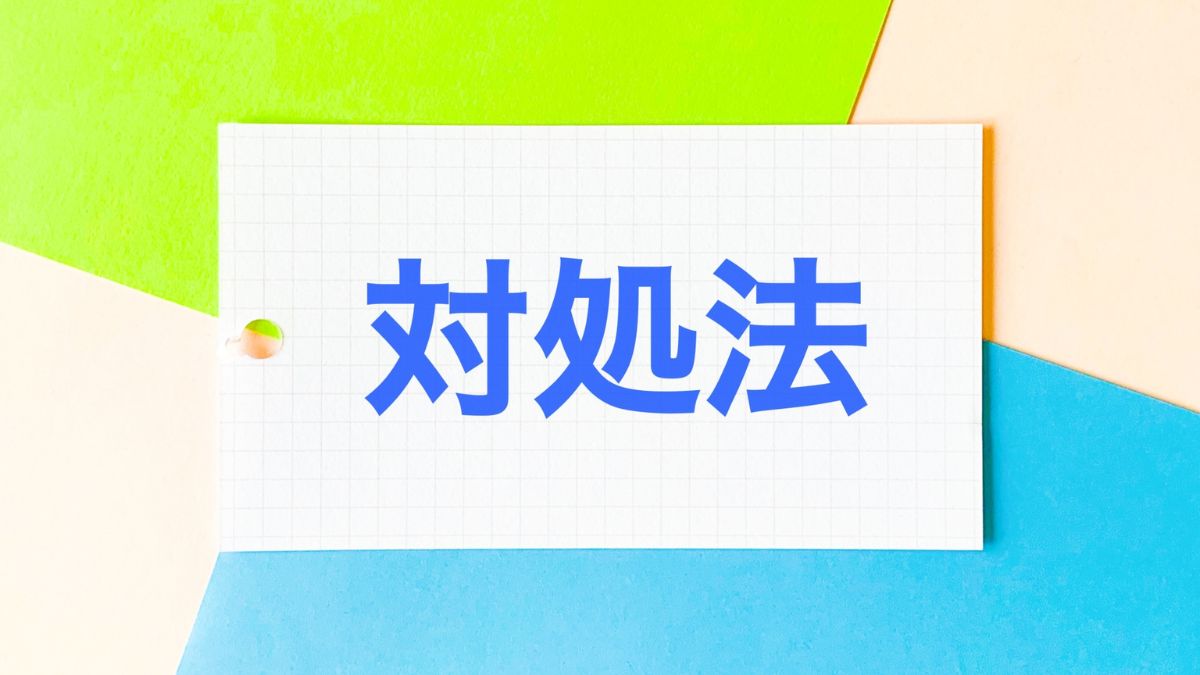
お守りをどうしてもあげたいときの対処法について解説します。
どうしても大切な人にお守りを渡したい、そんな場面もあると思います。
例えば、受験や就職、病気の回復など人生の節目や困難な時期に「少しでも力になりたい」と思う気持ちはとても自然なものです。
ただし、これまで説明したようにお守りには独特の文化的・宗教的背景があるため、贈るときは配慮が必要です。
ここでは、なるべくトラブルや誤解を避けて相手に気持ちが伝わる方法を解説します。
お守りを贈るときのちょっとした気遣いが、関係をより良いものにしてくれますよ。
事前に確認しておくこと
お守りを贈りたいと思ったら、まず相手がどう感じるかを考えてみてください。
人によっては、宗教的な理由や家庭の事情でお守りを受け取りたくない場合もあります。
また、すでにほかのお守りを持っている場合、「たくさん持って大丈夫?」と心配になる人もいます。
そのため、事前に「お守りを贈ってもいいか」や「困らないかどうか」軽く聞いてみるのが安心です。
ストレートに聞きづらいときは、「受験のときはお守り持つ派?」などと会話の中で自然に探るのもおすすめです。
相手の気持ちを確認せずに贈ってしまうと、意外なトラブルにつながることもあります。
ちょっとした確認が、お互いにとって気持ちの良いコミュニケーションにつながります。
新品のお守りの場合
お守りをあげる場合は、必ず新品のものを選びましょう。
一度自分が持ったり、袋から出したりしたお守りは「持ち主の運気が入っている」と考える人も多いため、渡すのは控えてください。
神社やお寺で授かったままの状態で相手に手渡すことがマナーです。
また、授与所でいただいた時の説明書やしおりも一緒に渡すと、相手が正しく扱いやすくなります。
「○○の神社でいただいた、学業成就のお守りだよ」など、どこの神社やお寺のお守りなのかも伝えてあげると安心感があります。
新品のお守りは「これからあなたのためにご利益をもたらしてくれるもの」として喜ばれやすいです。
贈る前に自分で封を開けたり、使ったりしないように注意してください。
清潔で気持ちよく受け取ってもらえるように、見た目にも気を配りましょう。
神社やお寺の説明を伝える
お守りには、それぞれ意味やご利益があります。
渡すときに「どんな意味が込められているのか」「どんなご利益があるのか」簡単に説明できると、相手も安心して受け取れます。
神社やお寺によっては、お守りの由来や使い方が書かれたしおりやパンフレットがついてくる場合もあります。
それを一緒に渡したり、神社やお寺のホームページなどを見せたりして、しっかり説明できると好印象です。
また、お守りには「お返し不要」など、相手に気を使わせない気配りも忘れずに伝えてください。
宗教やご利益の考え方は人それぞれ違うので、あくまでも「気持ちのお守り」として渡す意識が大切です。
説明があることで、相手も安心してお守りを受け取ることができます。
お守りをもらいたくないときの断り方

お守りをもらいたくないときの断り方や、受け取った後の対応方法について解説します。
お守りをもらいたくないと感じることは誰にでもあるものです。
宗教的な理由や家庭の方針、自分の価値観など、さまざまな理由で「ちょっと困る」と思う場合もあります。
贈る側は善意のつもりでも、受け取る側には事情があることも多いです。
断るときや受け取った後のマナーを知っておくと、不要なトラブルを避けてお互い気持ちよく対応できます。
ここでは、上手な断り方や、受け取ってしまった場合の対処方法も詳しく解説します。
角が立たない断り方
お守りを断りたいときは、相手の善意や気持ちを大切にしつつやんわり伝えるのがポイントです。
「気持ちだけで十分です」「ありがたいけど、家の宗教の都合で…」「もうすでに大切なお守りを持っているから」など、感謝の気持ちを伝えながら断ると角が立ちません。
「せっかく選んでくれたのにごめんね」と一言添えると、相手も納得しやすくなります。
どうしても断りづらい場合は、「受験のときはお守り持たない派なんだ」と自分のスタイルを理由にするのもおすすめです。
無理に受け取って後から困るよりも、最初に気持ちよく断る方が長い目で見ても良い関係が築けます。
相手の気持ちを大切にしながらも、自分の意思も伝えることが大切です。
受け取った後の扱い方
うっかりお守りを受け取ってしまった場合や、断れずにもらってしまった場合も焦る必要はありません。
まずは、贈ってくれた相手に感謝の気持ちを伝えましょう。
その後は、バッグや引き出しなど、自分が大切にできる場所にしばらく保管しておくのが一般的です。
お守りは「持つ人の気持ち」を大切にするものなので、自分なりに大切に扱えば問題ありません。
どうしても気になる場合や、複数持つことに抵抗がある場合は、神社やお寺に相談しても大丈夫です。
お守りを無理に持ち歩かず、自宅の神棚やきれいな場所に置いておくだけでも気持ちは伝わります。
大切なのは「もらった気持ちを無下にしないこと」です。
返却や処分方法
お守りを手放したいときや、どう扱っていいかわからないときは、神社やお寺で「お焚き上げ」をしてもらうのが一般的です。
お焚き上げは、感謝の気持ちを込めてお守りを返す日本独自の風習です。
近くの神社やお寺に持ち込むと、返納できる窓口が設けられている場合もあります。
郵送で受け付けているところも増えてきているので、どうしても持参できない場合は公式サイトで確認してみてください。
「処分するのは気が引ける」と思う人もいますが、感謝の気持ちを持って返せば問題ありません。
家庭ごみで処分するのはなるべく避けたほうが安心です。
どうしても処分に迷ったときは、贈ってくれた人や神社に相談してから決めると後悔しません。
お守りをあげることで起こるトラブルや体験談
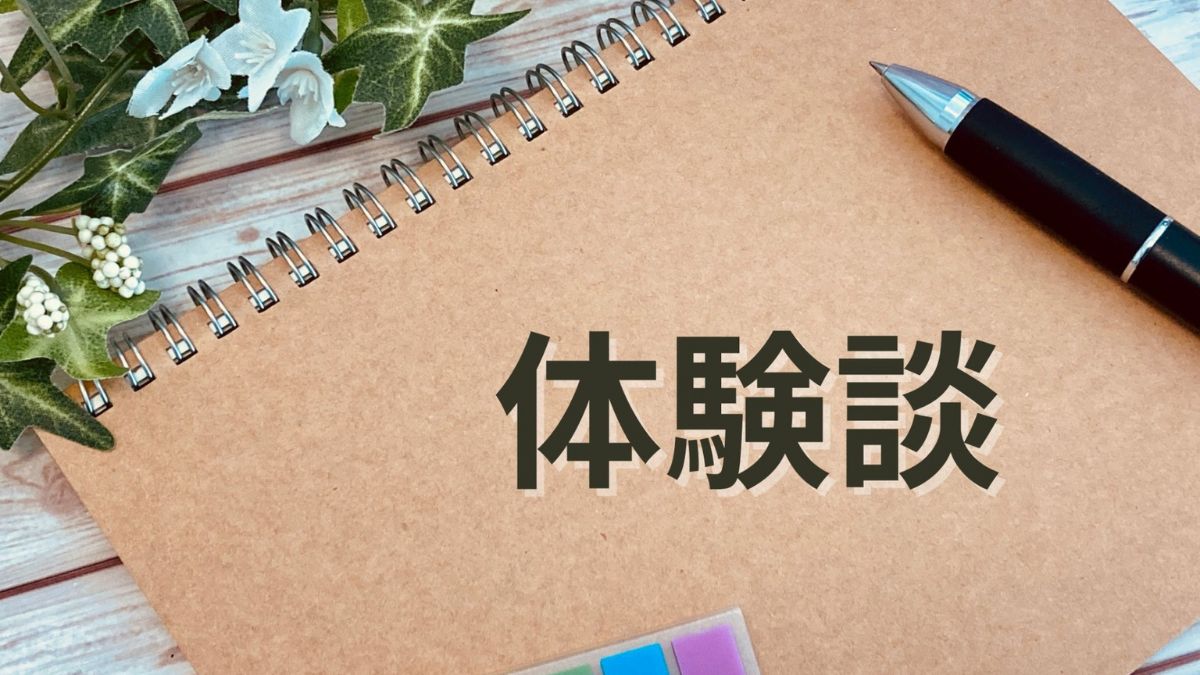
お守りをあげることで起こりやすいトラブルや、実際の体験談について紹介します。
お守りを贈る行為には善意が込められていますが、時には人間関係のトラブルや誤解を生んでしまうこともあります。
「せっかくの気持ちなのに…」と後悔したくないですよね。
ここでは、実際に起きやすいトラブルの事例や、贈るときに気をつけたいポイント、そして気持ちを伝える上手な方法までまとめました。
体験談を通して、お守りをあげる際の注意点や、より良い人間関係を築くヒントも一緒に紹介します。
思わぬトラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
人間関係のトラブル
お守りをあげたことがきっかけで、人間関係にすきま風が吹いてしまうことがあります。
たとえば、「自分は大丈夫だったけど、相手はお守りに抵抗があった」「贈ったことがきっかけで気まずくなった」などのケースです。
とくに職場や学校など、関係が浅い人にお守りを贈ると「重たく感じた」「宗教を押し付けられた気がした」などの理由で距離を置かれてしまうことも。
親しい友人同士でも、「本当に困ったときは相談してほしかった」と感じてしまう場合もあるので、贈るタイミングや相手との関係性には十分注意が必要です。
気持ちを押し付けないこと、相手の気持ちをよく考えて行動することが大切です。
誤解を招くケース
お守りをあげることで誤解が生まれることも少なくありません。
たとえば、恋愛関係の場合「特別な意味があるのかな?」と勘違いされてしまったり、逆に「なぜ自分だけ贈られたのか」と悩ませてしまうことも。
また、グループの中で一人だけにお守りを渡すと、「ひいきされている」と受け取られることがあります。
場合によっては、噂やトラブルの元になってしまうこともあるので配慮が必要です。
渡す相手の立場や、まわりの状況を考えて行動することで、余計な誤解を避けることができます。
相手がどう受け取るかを想像しながら贈り物を選ぶのがポイントです。
気持ちを伝える上手な方法
どうしてもお守りで気持ちを伝えたいときは、贈り方やタイミングを工夫するのがコツです。
まずは「無理に受け取らなくて大丈夫」「ご利益を願ってるから気軽にね」と言葉を添えると、相手のプレッシャーが和らぎます。
また、「受験や試合の応援」「体調を気遣う場面」など、特別な理由をしっかり伝えることで、善意が伝わりやすくなります。
贈る相手が迷わないように、お守りの意味や使い方もきちんと説明すると安心してもらえます。
お守り以外にも、応援メッセージや小さな手紙を添えるなど、相手に合わせてコミュニケーションを工夫すると、より気持ちが伝わります。
大切なのは「相手がどう感じるか」を第一に考えることです。
まとめ|お守りをあげるのはだめなのか
| 内容 | ページ内リンク |
|---|---|
| お守りをあげてはいけない理由 | こちら |
| お守りをあげても良い場合 | こちら |
| お守りを渡すときの注意点 | こちら |
| お守りをもらう側のマナー | こちら |
お守りをあげる行為は、古くからさまざまな考え方やマナーが受け継がれてきました。
善意のつもりでも、相手の宗教観や価値観、状況によってはトラブルや誤解の原因になることもあります。
新品のお守りであることや、渡す際の配慮や事前確認がとても大切です。
もらう側も気持ちよく対応できるよう、感謝の気持ちや断り方のマナーを知っておくと安心です。
お守りを贈る際には、「相手がどう感じるか」を常に意識して、思いやりのある行動を心がけてください。
疑問や不安がある場合は、神社やお寺の公式サイトや窓口で相談するのもおすすめです。