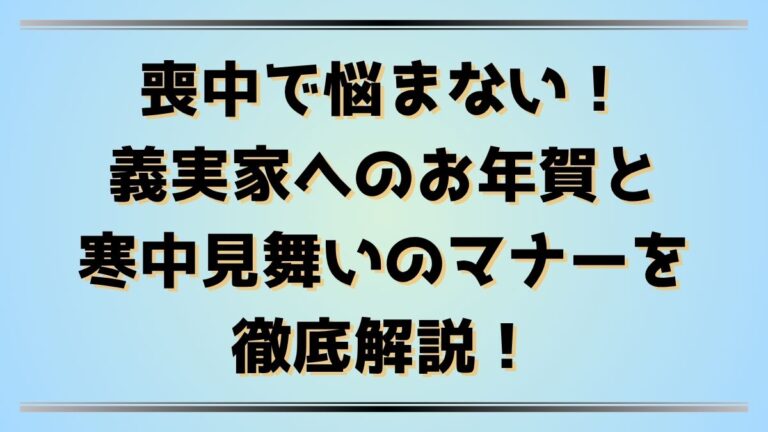喪中のお年賀と義実家対応について悩んでいませんか。
「義実家が喪中だけど、どうすれば失礼がないのか分からない」「お年賀の代わりに何を贈ればいい?」そんな疑問や不安を持つ方は多いはずです。
この記事では、喪中の義実家へのお年賀や寒中見舞いのマナー、挨拶の仕方、地域ごとの風習まで、気になるポイントを徹底解説します。
ケース別の対応例やおすすめの品物、よくある疑問Q&Aも充実しています。
あなたの大切な気遣いがしっかり義実家に伝わるよう、正しい知識と安心できる対応を一緒に身につけましょう。
この記事を読めば、喪中のお年賀や義実家対応の不安がスッキリ解消できますよ。
喪中のお年賀で義実家に失礼にならない対応ポイント

喪中のお年賀で義実家に失礼にならない対応ポイントについてお伝えします。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
義実家が喪中の場合に避けるべきこと
義実家が喪中の場合、まず大切なのは「お年賀」という言葉や熨斗(のし)を使った贈り物は避けることです。
お年賀は「新年をお祝いする」意味を持つため、喪中の家庭では控えるのが基本的なマナーとされています。
たとえば、お年賀用ののし紙に「御年賀」や「迎春」といったお祝いの言葉が入っている品物は避けるようにしましょう。
また、年始の挨拶状も「新年あけましておめでとうございます」といったお祝いの言葉は控え、シンプルなご挨拶やお伺いの言葉にとどめると失礼がありません。
どうしても贈り物をしたい場合は、「寒中見舞い」として、松の内(1月7日ごろ)を過ぎてから贈るようにするのが一般的です。
自分が喪中の場合に配慮するポイント
自分自身や配偶者が喪中の場合でも、義実家へのお年賀には配慮が必要です。
「自分はお祝いする気持ちになれないから」といって、お年賀や挨拶自体をしないという対応は、場合によっては義実家から誤解を招くこともあります。
お祝い事を控えたい気持ちを伝えつつ、「本年もどうぞよろしくお願いいたします」など、穏やかな言葉を選んで挨拶するのが安心です。
お年賀の品も、どうしても気になる場合は「寒中見舞い」として、時期をずらして贈る方法が選ばれています。
義実家の考え方もそれぞれ違うので、事前に相談するのもおすすめです。
お年賀ではなく寒中見舞いを贈る理由
喪中の期間は「お祝い」を控える風習があるため、代わりに「寒中見舞い」を贈るのが一般的です。
寒中見舞いは「寒さが厳しい時期に相手の健康を気遣う」意味合いが強く、祝い事とは違ったニュアンスで送ることができます。
年賀状やお年賀の代わりとして、松の内(1月7日または1月15日)を過ぎてから2月初旬ごろまでの間に届けるのがマナーです。
寒中見舞いは義実家だけでなく、親戚やお世話になった方への挨拶にも使えるため、とても便利です。
形式にこだわりすぎず、気持ちが伝わる文章や品物を選ぶのがおすすめです。
事前に義実家へ相談したほうが良い理由
喪中のお年賀や寒中見舞いは、家庭ごとの考え方や地域の風習によってマナーが異なります。
義実家が厳格な家の場合や、逆にあまり気にしない場合もあるので、事前に「今年はどうしましょうか?」と一言確認しておくと安心です。
とくに初めて喪中を迎えるときは、「どうしていいかわからない」という不安もあるかもしれません。
義実家に「今年はお年賀を控えさせていただき、寒中見舞いでご挨拶してもよろしいでしょうか?」などと相談すれば、丁寧な印象を持ってもらえます。
相手の希望に合わせる姿勢を見せることで、無用なトラブルを防ぐことができます。
贈って喜ばれる寒中見舞いのおすすめ
寒中見舞いの品物は、お菓子や飲み物、タオル、カタログギフトなど「消え物」と呼ばれる消耗品が人気です。
理由は、後に残るものや華美なものは「お祝い」を連想させるため、喪中の時期には避けたほうが良いとされるからです。
たとえば、上品な和菓子や高級なお茶、地域の特産品なども喜ばれやすいです。
家族構成や好みに合わせて選ぶと、より気持ちが伝わりやすくなります。
包装ものし紙も、無地や「寒中見舞い」と書かれたシンプルなものを選びましょう。
避けたほうがよい品物や注意点
喪中の贈り物で避けたほうが良い品物には、「お祝い」を連想させるものや、日常使いしづらいものがあります。
たとえば、赤や金など派手な包装紙・リボン、鯛や昆布巻きなど「おめでたい」食材、花束や鉢植えも控えると安心です。
また、現金やギフト券は相手との関係性によっては失礼にあたる場合もあるので注意が必要です。
贈る時期やメッセージ内容にも気をつけ、相手を思いやる気持ちを第一にしましょう。
疑問があれば、遠慮せず義実家に確認するのが最善策です。
義実家が喪中のときに贈る寒中見舞いのマナー

義実家が喪中のときに贈る寒中見舞いのマナーについて詳しく解説します。
それぞれ順番に解説していきます。
寒中見舞いを贈るタイミングと期間
寒中見舞いは、松の内が明けてから立春まで(1月8日~2月3日ごろ)に贈るのが一般的です。
地域によって松の内が1月7日までか、15日までか異なりますが、多くの場合は1月8日以降が目安になります。
年賀状やお年賀のやり取りを控えていた場合、この時期に寒中見舞いとして改めてご挨拶を送ることで、気遣いを伝えることができます。
立春を過ぎてしまった場合は「余寒見舞い」として出すことも可能です。
時期を間違えず、寒い時期をねぎらう気持ちを添えて贈ることが大切です。
品物選びとおすすめの例
寒中見舞いの品物には、義実家の家族構成や好みを考えて選ぶことがポイントです。
和菓子、洋菓子、上質なお茶、ジュースやコーヒーなどの飲み物、タオルや日用品など、消耗品が選ばれることが多いです。
とくに義実家には、家族みんなで楽しめる個包装のお菓子や、少し上質な生活用品が人気です。
地域の特産品や旬の果物も、時期によっては喜ばれます。
高額すぎる品や豪華すぎるもの、長く残る記念品などは喪中の時期には避けた方が無難です。
のし紙や表書きの正しい書き方
寒中見舞いの品には、紅白の水引きや「御年賀」の表書きは使わず、白無地ののし紙または掛け紙を選びます。
表書きは「寒中見舞い」と書くのが一般的です。
名前はフルネームで記載し、送り主が家族の場合は世帯主の名前で統一することが多いです。
のしの水引きも、色付きのものではなく、シンプルなデザインのものを選ぶと失礼がありません。
もしお店で購入する場合は「寒中見舞い用」と伝えると、適したのし紙を用意してくれます。
寒中見舞いの挨拶文例
寒中見舞いの挨拶文には、相手の体調や心情を気遣う文章を心がけましょう。
お祝いの言葉や年始の定型文は使わず、「寒さが厳しい折いかがお過ごしでしょうか」など、季節の挨拶が基本です。
たとえば、「寒中お見舞い申し上げます。このたびご不幸があったことを心よりお悔やみ申し上げます。寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください」などが無難な文例です。
もし親しい関係なら、家族や子どもの様子なども一言添えるとより温かい印象になります。
あくまで相手の気持ちに寄り添う内容を心がけましょう。
ネット通販で贈る場合のコツ
ネット通販で寒中見舞いの品を選ぶ場合、のし紙やラッピングの対応が可能か必ず確認しましょう。
大手通販サイトやギフト専門店では、注文時に「寒中見舞い」と指定できるオプションが用意されていることが多いです。
先方の在宅状況や受け取りやすいタイミングも考慮し、事前に到着予定日を伝えておくと安心です。
メッセージカードや手紙を同封できる場合は、必ず感謝や気遣いの言葉を添えましょう。
配送先の住所や受取人名に間違いがないかも、しっかり確認してから注文してください。
気遣いが伝わるメッセージ例
寒中見舞いの品と一緒に添えるメッセージには、相手の健康と心情を気遣う短い言葉が効果的です。
たとえば、「寒さ厳しい折、ご家族皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます」といった表現が丁寧です。
また、「本年もどうぞよろしくお願いいたします」など、お祝いを連想しない言い回しを選びます。
自分の気持ちを率直に伝えることで、形式にとらわれすぎない心遣いも感じてもらえます。
一言メッセージが添えてあるだけでも、義実家に気持ちがしっかり伝わります。
自分や配偶者が喪中のとき義実家への挨拶はどうする?

自分や配偶者が喪中のとき義実家への挨拶はどうするのがよいかについてまとめます。
それぞれポイントを押さえて説明します。
挨拶の言葉選びと伝え方
自分や配偶者が喪中の際、義実家への挨拶で一番大切なのは言葉選びです。
「あけましておめでとうございます」は避けて、「本年もどうぞよろしくお願いいたします」や「昨年は大変お世話になりました」など、丁寧な表現にしましょう。
手紙や寒中見舞いでは「寒さ厳しい折、ご自愛ください」など、相手の健康を気遣う言葉がベストです。
面と向かって挨拶する場合も、しっかり気持ちを伝えることで誠実な印象になります。
もし迷った場合は、事前に義実家に確認してみると安心です。
年始の訪問や電話で気をつけること
喪中のときに年始の訪問や電話をする場合、新年の華やかな雰囲気を強調しないことが大切です。
玄関飾りやおせち料理など、いわゆる「お祝いムード」を前面に出すのは避けます。
電話やメッセージも、明るく「新年おめでとうございます」と言うのではなく、「昨年はご心配をおかけしました」など、落ち着いた挨拶にするのがマナーです。
義実家が気にしないタイプなら、通常通り訪問しても大きな問題はありませんが、一言「喪中なのでお祝いは控えさせていただきます」と伝えると好印象です。
自分の気持ちだけでなく、相手の考え方にも配慮することが大切です。
義実家との関係性で変わる配慮
義実家との関係性によって、挨拶や対応の仕方も変わってきます。
普段から親しい場合は、少し砕けた表現や家族の近況を添えるのも良いですが、あまり親しくない場合や格式を重んじる家なら、より丁寧な言葉や形式を守るのが無難です。
義両親が年配で伝統を大事にする傾向なら、基本のマナーを守りつつ、気持ちを込めて対応すると安心です。
逆に「全く気にしなくていいよ」と言われた場合でも、最低限の気遣いを忘れずに、失礼のないようにしましょう。
迷ったときは「念のため今年は控えめに」と相談してみてください。
うっかりお年賀を渡してしまった場合のフォロー
喪中であることをうっかり忘れてお年賀を渡してしまった場合は、すぐに気付いてお詫びの一言を伝えることが大切です。
「おめでたいものを差し上げてしまい、申し訳ありません」と正直に伝えれば、相手も気にしすぎずに受け取ってくれることがほとんどです。
気になる場合は、後日改めて寒中見舞いの手紙やお菓子などを送り、「先日は失礼いたしました」とお詫びの気持ちを添えましょう。
大切なのは気持ちと誠実な対応です。
深く悩みすぎず、丁寧にフォローすれば義実家との関係が悪くなることはほとんどありません。
地域や家ごとに異なる喪中のお年賀対応の違い

地域や家ごとに異なる喪中のお年賀対応の違いについて解説します。
それぞれのポイントを順番に見ていきます。
地方による風習や違い
日本各地では、喪中のお年賀や寒中見舞いの対応に地域ごとの風習があります。
関東では松の内が1月7日まで、関西では1月15日までとされているため、寒中見舞いを贈る時期も異なる場合があります。
また、北陸や東北では、寒中見舞いの代わりに「お伺い」や「お見舞い」という形式をとる地域もあります。
一部地域では、お正月飾りやおせち料理も完全に控える場合がある一方、故人と関係の深かった家庭では「静かなお正月」を迎える程度にとどめることもあります。
義実家が遠方の場合は、現地の風習やマナーを事前に調べておくのが安心です。
義実家と実家で違う場合の対処
自分の実家と義実家で喪中時のお年賀や寒中見舞いの対応が異なるケースも少なくありません。
たとえば、実家では寒中見舞いを重視するけれど、義実家では何も送らないのが普通という場合もあります。
このようなときは、どちらか一方のやり方を押し付けるのではなく、それぞれの家の方針を尊重することが大切です。
どうしても迷う場合は、「実家ではこのようにしていますが、義実家のご意向に合わせてもよいですか」と相談するとトラブルになりません。
両家のやり方に違いがあることを素直に伝え、お互いが納得できる形で対応を決めることが円満な関係につながります。
家ごとのルールが分からないときの調べ方
義実家や自分の家で喪中のお年賀や寒中見舞いにどんなルールがあるか分からない場合は、親戚や兄弟、近しい親族に相談するのが一番です。
直接義父母に聞きづらい場合は、親族に「今年はどうする予定ですか?」とさりげなく尋ねてみるのも有効です。
また、地域のしきたりやマナーを調べたいときは、市区町村の公式サイトや地域情報誌を活用する方法もあります。
最近では、葬儀社やマナー専門サイトで最新の情報を確認することもできます。
独自ルールや暗黙の決まりがある家庭もあるので、事前に把握しておくと余計な心配をせずに済みます。
喪中のお年賀と義実家対応に関するよくある疑問Q&A

喪中のお年賀と義実家対応に関するよくある疑問Q&Aをまとめました。
みなさんが気になりがちなポイントを一問一答形式で解説します。
お年賀をもらったときの対応
喪中でお年賀をいただいた場合は、素直に感謝の気持ちを伝えることが大切です。
「お気遣いありがとうございます」と伝えたうえで、無理に断る必要はありません。
ただし、どうしても気になる場合は「実は喪中のため、本年はお祝い事を控えております」と一言添えると角が立ちません。
お返しは寒中見舞いや簡単なお礼の品を贈る形で問題ありません。
受け取ったものに対する感謝と気遣いを言葉にして伝えましょう。
二重に喪中が重なった場合の配慮
自分側と義実家側、双方が喪中という「二重喪中」になるケースもあります。
この場合は、基本的にお祝い事や贈答をすべて控え、寒中見舞いなどでご挨拶するのが最も無難です。
どちらの家の習慣も尊重しつつ、無理に形式にこだわりすぎないことも大切です。
気持ちを込めた手紙やメッセージでお互いの心をいたわる配慮が求められます。
迷う場合は、義実家と実家の両方に相談して決めると安心です。
子どもがいる場合の挨拶や対応
子どもがいる場合、普段通り年始の挨拶やお年玉をどうするか迷うことも多いです。
喪中であっても、お年玉は「お祝い」ではなく「お小遣い」として渡す家庭が多く見られます。
ただし、のし袋の表書きを「お年玉」ではなく「おこづかい」や「ご厚志」とするケースもあります。
義実家や親戚の意向に合わせて対応しましょう。
子どもには「今年は喪中なので、いつもと少し違う挨拶になるよ」と伝えておくと混乱しません。
宗教や信仰による違いについて
仏教・神道・キリスト教など、宗教によって喪中や年賀の考え方が異なる場合があります。
たとえば仏教でも宗派によっては新年を静かに迎えるだけで、特別な制約がないこともあります。
神道では喪中の期間が比較的短く、神社への参拝を避ける程度という場合もあります。
キリスト教や無宗教の場合は喪中を気にしない家庭も多いですが、義実家の価値観に合わせて行動するのが安心です。
迷った場合は遠慮せず、「今年はどのようにするのがよいですか」と率直に尋ねましょう。
まとめ|喪中のお年賀や義実家への対応で迷わないマナー
| 主な対応ポイント |
|---|
| 義実家が喪中の場合に避けるべきこと |
| 自分が喪中の場合に配慮するポイント |
| お年賀ではなく寒中見舞いを贈る理由 |
| 事前に義実家へ相談したほうが良い理由 |
| 贈って喜ばれる寒中見舞いのおすすめ |
| 避けたほうがよい品物や注意点 |
喪中のお年賀や義実家への対応は、誰でも迷ってしまいがちなテーマです。
大切なのは形式やルールにとらわれすぎず、相手の気持ちを思いやった行動を心がけることです。
義実家が喪中の場合は、お年賀を控えて寒中見舞いを贈る、事前に相談する、迷ったら丁寧に確認するなど、少しの配慮が関係性をより良くしてくれます。
地域や家ごとにルールの違いがあっても、気持ちのこもった対応ならきっと伝わります。
不安なときは身近な親族や公式サイトで情報をチェックしておくと安心です。