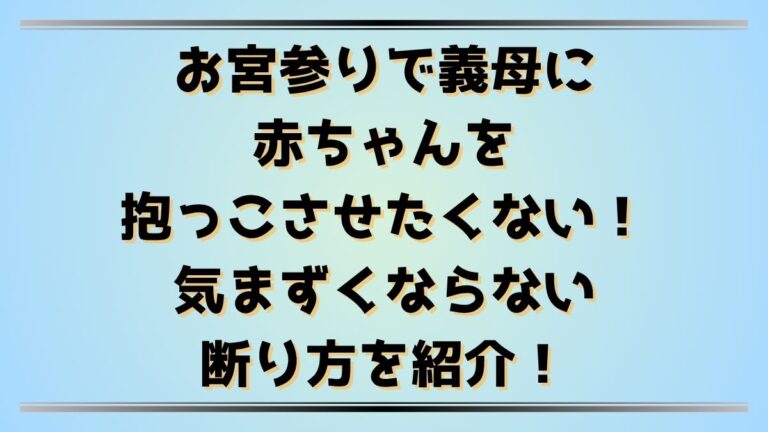お宮参りで義母に赤ちゃんを抱っこさせたくない…そんな悩みを抱える方はとても多いです。
この記事では、義母が抱っこを希望する理由や、抱っこさせたくないと感じる母親の本音、角を立てずに伝えるコツ、実際に断った後のフォローや家族全体が納得できる進め方まで詳しく解説します。
「義母との関係が気まずくならないか」「断ったら後悔しそう」など、不安を持つすべての方に安心してもらえるような答えと、みんなが笑顔になれるヒントをまとめました。
この記事を読むことで、自分の気持ちを大切にしながら、お宮参りを家族の素敵な思い出にできる方法が分かります。
ぜひ最後までご覧ください。
お宮参りで義母に赤ちゃんを抱っこさせたくないときの悩みと対処法

お宮参りで義母に赤ちゃんを抱っこさせたくないときの悩みと対処法について解説します。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
お宮参りで義母が抱っこしたがる理由
お宮参りのときに義母が赤ちゃんを抱っこしたがる理由には、さまざまな背景があります。
ひとつは「自分の孫」という実感を持ちたいという思いです。
お宮参りは家族が一堂に会する特別なイベントであり、義母としては「おばあちゃん」としての立場をしっかりアピールしたい気持ちがある場合も多いです。
また、昔はお宮参りの赤ちゃんは義母や祖母が抱っこするのが一般的だった時代もあり、「こうするもの」という固定観念がある場合も多いです。
写真撮影や親戚への報告などのタイミングで、義母が自然な流れで抱っこしようとすることもよくあります。
とくに地方によっては「最初の抱っこは父方の祖母がするべき」といった慣習が残っているところもあり、無意識にその流れになってしまうことも。
こうした義母側の気持ちや背景を知っておくだけでも、気持ちのすれ違いを減らすことができます。
義母に抱っこさせたくないときの正直な気持ち
本音では義母に赤ちゃんを抱っこさせたくないと感じる理由は人それぞれですが、かなり多くの人が同じ悩みを抱えています。
「まだ赤ちゃんが小さいので心配」「正直なところ、義母の抱っこの仕方が不安」「母親として自分が抱っこしていたい」という気持ちは決して珍しくありません。
また、衛生面や体調面が心配という人も多いです。
たとえば風邪の流行時期や、赤ちゃんが生まれて間もない場合は、赤ちゃんの健康を優先したい気持ちが強くなります。
さらに、普段の義母との関係性や過去の言動、距離感が理由で「赤ちゃんを預けたくない」と感じる場合も。
自分の感情を否定する必要はありませんし、母親の直感も大事な判断材料です。
義母に抱っこさせないことへの罪悪感や葛藤
「抱っこさせたくない」と感じても、実際に断るのは簡単ではありません。
「自分がわがままなのかな」「義母に悪く思われるのでは」と葛藤する人が本当に多いです。
実際にSNSやママ向けの情報サイトには「断り方が分からない」「夫に相談しても協力してくれない」といった体験談もたくさん見られます。
特にお宮参りというハレの日は「みんなが気持ちよく過ごしてほしい」と考えるからこそ、余計に罪悪感が強くなりがちです。
でも、誰かが傷つくのを我慢してすべて丸く収める必要はありません。
自分の気持ちを大切にすることは、赤ちゃんのためでもあります。
義母との関係を悪化させないための考え方
義母に赤ちゃんを抱っこさせないことで、今後の関係が悪化しないかと心配になる人も多いです。
実際は、きちんと理由を伝えたり、事前に夫や家族と話し合っておけば、大きなトラブルになりにくいです。
体調や衛生面、赤ちゃんの負担をしっかり伝えることで、義母も「仕方ない」と納得しやすくなります。
当日までに夫にも協力してもらい、「今回はこういう理由で母親が抱っこする」と伝えてもらうのも有効です。
また、お宮参りが終わった後に写真を共有したり、他の場面で義母に赤ちゃんと触れ合う機会を作ることで関係性を良好に保てます。
お宮参りの赤ちゃんの抱っこは誰がするものなのか

お宮参りの赤ちゃんの抱っこは誰がするものなのか、具体的に解説します。
続いて、お宮参りの抱っこのマナーや家族のパターンについて詳しく見ていきます。
一般的なお宮参りの流れと抱っこのマナー
お宮参りの流れや抱っこのマナーは、時代や地域によって変化しています。
昔は父方の祖母が赤ちゃんを抱っこするのが「正式」と言われていた時代もありました。
その背景には「家の後継ぎ」や「嫁いだ家の祖母が子どもを守る」という意味合いがありました。
現在では「誰が抱っこしてもよい」という考え方が主流になっており、形式にこだわらない家族が増えています。
とくに神社のご祈祷や写真撮影では、母親や父親が抱っこするパターンもよく見られます。
マナーとしては「赤ちゃんと母親の体調を最優先」「主役である家族が納得する形を選ぶ」のが大切です。
神社によっては「赤ちゃんは母親が抱っこしてください」と案内されることもあります。
母親や父親が抱っこする家庭のパターン
最近は母親や父親が赤ちゃんを抱っこしてお宮参りを行う家庭もとても多くなっています。
「初めてのお宮参りは母親が赤ちゃんと一緒にいたい」「夫婦で一緒に記念写真を撮りたい」という希望も増えています。
とくにコロナ禍以降は、母親や父親が直接抱っこするスタイルが一般的になりつつあります。
母親が体調的にきつい場合は、父親が抱っこすることも珍しくありません。
柔軟な考え方が広がっているため、誰が抱っこするかは各家庭の事情や本人たちの希望が優先されるようになっています。
祖父母が抱っこする場合の習慣や地域差
一方で、今でも祖父母、とくに父方の祖母が抱っこする地域もあります。
とくに関西地方や伝統を重視する家庭では「祖母が抱っこ」と決めていることが多いです。
親族やご近所の目を気にして「昔からのやり方に合わせるべきか」と悩む人もいます。
ですが、全国的には地域差がだんだんと薄れ、「その家族が納得できるやり方でOK」という意識が広がっています。
慣習に縛られすぎず、家族や赤ちゃんの健康と気持ちを第一に考えましょう。
家族の意見が分かれるときの調整方法
家族の間で「誰が抱っこするか」について意見が分かれる場合は、事前の話し合いがとても大切です。
両家で意見が食い違うときは、夫婦でしっかりと自分たちの考えをまとめておき、穏やかに話し合いましょう。
「赤ちゃんの体調が不安なので母親が抱っこしたい」「写真撮影のときは父親が抱っこする」など、場面ごとに役割を分けることもできます。
無理に誰かの意見に合わせる必要はありません。
家族で納得できる妥協点を探して、お宮参りをみんなが良い思い出にできるよう工夫しましょう。
義母に抱っこさせたくない理由と伝え方のコツ

義母に抱っこさせたくない理由と伝え方のコツについて具体的に解説します。
ここからは、義母に抱っこを断りたい場合の理由や伝え方を詳しく見ていきます。
衛生面や体調面の心配を理由にする場合
義母に赤ちゃんを抱っこさせたくないとき、最も自然な理由が「衛生面や体調面の心配」です。
赤ちゃんは生後間もなく免疫力が弱いので、感染症や風邪をもらうリスクを減らしたいという考えは、ごく当然のものです。
たとえば「最近は風邪が流行っているので」「赤ちゃんがまだ体調が不安定なので」という伝え方は、角が立ちにくく理解も得やすいです。
どうしても断りにくい場合は、かかりつけ医のアドバイスや育児本など、第三者の意見を引用するのも有効です。
「お医者さんから言われているので」と伝えると、義母も納得しやすくなります。
とくに季節の変わり目やインフルエンザ流行時期は、赤ちゃんの健康を理由にすると角が立ちません。
義母本人のためにもなると伝えることで、気持ちよく納得してもらいやすいです。
きょうだいや他の家族の希望を理由にする場合
自分だけの希望だと伝えづらい場合は、きょうだいや他の家族の意向を理由にするのも一つの方法です。
たとえば「上の子がママと一緒じゃないと不安がるので」「おじいちゃんも抱っこを楽しみにしているみたい」など、周囲の状況をうまく使うと断りやすくなります。
家族みんなが納得できる形を考えている、と前向きな理由を伝えれば角も立ちにくいです。
お宮参りは親族のバランスを取るイベントでもあるので、みんなで主役の赤ちゃんを見守る形にすると、義母も不満を感じにくくなります。
伝え方次第で、「あなたが嫌なのではなく、みんなで楽しみたい」という空気を作ることが大切です。
事前に伝えておくメリット
当日に急に断るのはトラブルのもとになりやすいので、できれば事前に伝えておくのが理想です。
あらかじめ「今回のお宮参りでは、母親が抱っこする予定なんです」と言っておけば、当日の気まずさも減ります。
夫から事前に話をしてもらうのも効果的です。
また、LINEや電話で「赤ちゃんの体調が不安定で」などと伝えておくことで、義母も覚悟を持って当日を迎えられます。
事前にきちんと説明しておけば「私だけ仲間外れにされた」といった誤解も防げます。
当日の対応で気をつけるポイント
どうしても当日に断らなければならない場合は、できるだけ柔らかい表現を使いましょう。
「今日は赤ちゃんの調子が良くないみたいで」「移動が多くて疲れてしまっているみたいです」など、赤ちゃんの体調や気持ちを主語にすると角が立ちにくいです。
また、写真撮影やご祈祷の場面では「今は私が抱っこします」と自然な流れを作りやすいです。
その場限りで角を立てずに済ませたいときは、「あとで落ち着いたときに」「また次の機会に」とフォローの言葉を添えておくと良いです。
あくまで赤ちゃんのためというスタンスを崩さず、穏やかに伝えることが大切です。
義母に抱っこを断った後のフォローとケア

義母に抱っこを断った後のフォローとケアについて詳しく解説します。
断った後のフォローや関係性を保つコツを順番に見ていきましょう。
断った後にできるフォローの言葉
義母に「抱っこは遠慮したい」と伝えた後は、フォローの言葉を忘れずに伝えることで、気まずさをやわらげることができます。
たとえば「今日は赤ちゃんの調子が良くなかったけれど、次の機会にぜひお願いします」や、「お宮参りで一緒に写真を撮れて嬉しかったです」など、義母が主役の一員であることをアピールできる言葉を添えるのが効果的です。
写真を後日シェアする、赤ちゃんの動画を送るなど、小さな気遣いが相手の心を和らげます。
「お宮参りの思い出をみんなで大切にしたい」という気持ちを伝えることも大切です。
義母の気持ちに寄り添う姿勢を示すことで、納得してもらいやすくなります。
義母との距離感を保つ工夫
義母との距離感は、近すぎても遠すぎてもトラブルの元になります。
「必要以上に気を使いすぎない」「干渉されすぎたときは夫を間に入れる」など、無理のない範囲で自然体を心がけましょう。
定期的に赤ちゃんの写真を送ったり、ちょっとした成長を報告するだけでも、義母との良い距離感を保つことができます。
連絡や報告は無理のない頻度で十分です。
家族の形はそれぞれなので、「うちの距離感」で大丈夫という意識を持つとストレスも減ります。
夫や家族に協力してもらう方法
義母とのコミュニケーションで一番重要なのは夫のサポートです。
妻だけがすべてを抱え込まず、事前に夫と「どうするか」「どこまで対応するか」を話し合っておきましょう。
夫から義母に説明してもらうことで、伝わり方が柔らかくなることも多いです。
家族の行事はみんなで協力するもの、というスタンスを忘れずに進めてください。
親戚やきょうだいの協力が必要なときは、全員で意見を合わせるのも有効です。
今後の関係づくりで意識したいこと
お宮参りの場面だけでなく、今後の義母との関係づくりも大切です。
無理して仲良くする必要はありませんが、適度な距離感と感謝の気持ちは大切にしましょう。
ときどき「赤ちゃんが成長したら一緒にお出かけしましょう」「〇〇のときはぜひお願いします」と前向きな約束をすると、お互いに良い関係が続きます。
小さなことでもお礼や報告を欠かさないことで、義母も安心できます。
家族全体が無理せず笑顔でいられる関係づくりを意識しましょう。
お宮参りで後悔しないための自分と家族の向き合い方

お宮参りで後悔しないための自分と家族の向き合い方についてまとめます。
後悔のないお宮参りのためにできることを順番に解説します。
自分の気持ちを大切にするための考え方
お宮参りは家族にとって大切なイベントですが、まず自分の気持ちを大切にすることが一番重要です。
「本当はこうしたい」「赤ちゃんのことが一番心配」という自分の直感や思いを無理に押し殺す必要はありません。
母親や父親としての不安や疑問を持つのは当たり前なので、正直な気持ちを自分で受け止めることが大切です。
誰かの常識や期待に合わせすぎてストレスを感じるより、自分たち家族の幸せを第一に考えて良いのです。
自分を責めずに素直な気持ちを受け入れることで、お宮参り当日も自然体で過ごせます。
家族全体の幸せを考える視点
お宮参りは家族全員が参加する行事なので、自分だけでなく家族全体の気持ちも考えることが大切です。
両親や義母、夫、きょうだいなど、みんなの意見を少しずつ聞いて、納得できる落としどころを探していきましょう。
ときにはぶつかることもありますが、お互いが「赤ちゃんのために良い形」を目指す気持ちがあれば必ず前向きに進めます。
家族の幸せは一人で作るものではありません。
みんなで協力してお宮参りを素敵な思い出にできるよう話し合いを大切にしましょう。
失敗しないための事前準備
お宮参りで後悔しないためには、事前準備がとても大切です。
誰が抱っこするか、どうやって進行するか、どのタイミングで写真を撮るかなど、あらかじめ家族で共有しておきましょう。
当日バタバタしてしまうと、想定外のトラブルが起きやすくなります。
事前に連絡や相談を済ませておくことで、余計な気まずさを防げます。
また、体調や天候に合わせて柔軟に対応できるよう心の準備も大切です。
他のママの体験談やアドバイス
実際にお宮参りを経験したママたちの体験談はとても参考になります。
「どうしても義母に抱っこさせたくなかったけど、事前に夫から説明してもらって無事に終わった」「親族との距離感に悩んだけれど、赤ちゃんの健康を理由に乗り切った」などの声も多いです。
SNSやママ向けサイトでは最新の体験談やアドバイスがたくさんシェアされています。
自分一人で悩まず、他の人の意見や実例を知ることで新しい気づきが得られます。
困ったときは同じ悩みを持つ人の意見を取り入れてみてください。
まとめ|お宮参りで義母に赤ちゃんを抱っこさせたくない悩みの解決法
| お宮参りで義母に抱っこさせたくないときのポイント |
|---|
| 義母が抱っこしたがる理由 |
| 抱っこさせたくない正直な気持ち |
| 罪悪感や葛藤への向き合い方 |
| 関係を悪化させない考え方 |
お宮参りで義母に赤ちゃんを抱っこさせたくないという悩みは、実はとても多くの家庭で生まれています。
義母がなぜ抱っこしたがるのか、抱っこさせたくない気持ちが生まれるのは自然なことか、どう断れば関係を悪くせず自分の気持ちも守れるのかを、段階ごとに解説しました。
本音を押し殺す必要はなく、自分の気持ちや赤ちゃんの健康を第一に考えることが大切です。
家族それぞれの立場や気持ちを尊重し、事前の話し合いや柔軟な対応を心がけることで、気まずい空気を防ぐことも可能です。
自分や家族が納得できるお宮参りを実現するために、この記事が少しでも参考になればうれしいです。
関連情報:
【衝撃】孫のお宮参りに普段着で現れた義父母、そして義母の心無い一言に凍り付く…|お宮参りトラブル体験談(ママリ)