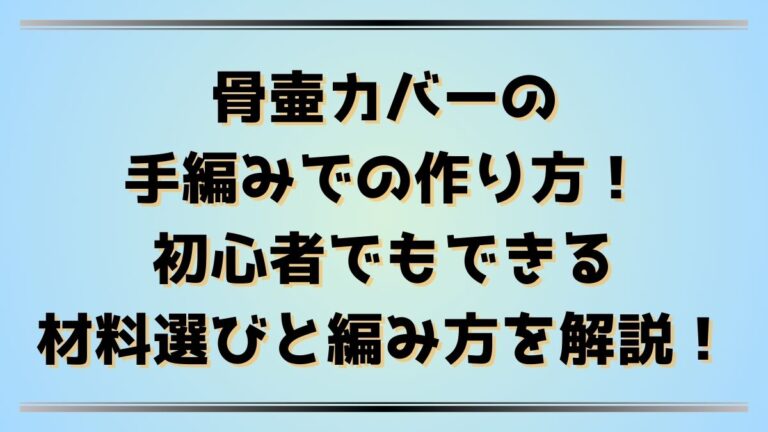骨壷カバーの手編みでの作り方を探している方へ、大切な人やペットを想いながら編むあたたかい時間を過ごせる方法をご紹介します。
この記事では、初心者でも挑戦できる材料選びから、編み方の基本、丁寧な手順、さらにアレンジ方法まで分かりやすくまとめています。
手作りのカバーは市販品にはない特別な温もりがあり、故人やペットへの想いを込められるのが魅力です。
編み方を覚えることで、自分らしいデザインのカバーを作ることができ、安心感と達成感を味わえます。
この記事を読めば、世界に一つだけの骨壷カバーを自分の手で完成させる未来が見えてきます。
ぜひ最後まで読んで、心を込めた手作りに挑戦してみてくださいね。
骨壷カバーの手編みでの作り方の基本

骨壷カバーの手編みでの作り方の基本を知ろうについて解説します。
それでは順番に説明していきますね。
初心者に必要な材料
骨壷カバーを手編みするためには、まず必要な材料を揃えることが大切です。
基本的に必要となるのは「毛糸」「かぎ針」「はさみ」「とじ針」「メジャー」の5点です。
毛糸は柔らかく手触りが良いものを選ぶと、仕上がりも温かみのあるカバーになります。
特に骨壷は陶器や金属が多いため、傷を防ぐためにアクリルやウール素材の毛糸が好まれる傾向があります。
また、とじ針は編み終わりの糸を処理するために必須で、メジャーは骨壷のサイズを正確に測るために使います。
初心者の方は、100円ショップや手芸店で揃えられるスターターセットを購入するのもおすすめです。
セットには必要な道具が揃っているので、迷わず始められますよ。
さらに、骨壷カバーをきれいに仕上げるためには、毛糸の太さに合ったかぎ針を使うことが重要です。
材料選びでつまずくと完成度に影響するので、しっかり確認してから準備してくださいね。
毛糸の選び方
毛糸選びは、仕上がりの雰囲気を決める重要なポイントです。
骨壷カバーは常に目に触れるものなので、色や質感にはこだわりたいところです。
おすすめはアクリル毛糸やウール毛糸で、柔らかく扱いやすいものが向いています。
アクリル毛糸は耐久性が高く、カラーバリエーションも豊富なので自由にデザインできます。
ウール毛糸は保温性があり、ナチュラルな雰囲気が出せるのが特徴です。
逆にナイロンや細すぎる糸は形が崩れやすいため、初心者にはあまり向きません。
また、骨壷の色に合わせたコーディネートも大切で、白い骨壷には淡いパステルカラー、黒やグレーの骨壷には落ち着いたトーンの毛糸を使うと調和がとれます。
色の組み合わせ次第で「優しい雰囲気」「モダンな雰囲気」など印象を大きく変えられるので、用途に合わせて考えてみてください。
毛糸選びは楽しい時間でもあるので、ぜひ手に取って選んでみてくださいね。
かぎ針のサイズと種類
かぎ針は毛糸と同じくらい大切な道具です。
サイズが合っていないと、編み目がきつすぎたり緩すぎたりして、きれいな骨壷カバーが完成しません。
基本的には毛糸のラベルに推奨されるかぎ針の号数が書かれているので、それを参考にすると間違いありません。
初心者には「6号〜8号」のかぎ針が扱いやすいとされています。
また、かぎ針には金属製、竹製、プラスチック製などがあり、それぞれ使い心地が異なります。
金属製はすべりが良くスピーディーに編めますが、長時間使うと手が疲れやすいです。
竹製は軽くて手に優しいため、初心者にはおすすめです。
プラスチック製は安価ですが、強度が低いので耐久性に欠けます。
最初は竹製を選んで、慣れてきたら金属製にチャレンジすると良いでしょう。
かぎ針の選び方次第で作業のしやすさが大きく変わるので、自分に合ったものを見つけてください。
基本的な編み目の使い方
骨壷カバーを編むときに必要な基本的な編み目は「鎖編み」「細編み」「長編み」の3つです。
鎖編みは編み始めやつなぎ目に使われ、作品の基礎を作る大切な編み方です。
細編みは隙間が少なくしっかりした布地を作れるため、骨壷カバーの本体部分に適しています。
長編みは高さが出るので、模様やデザインを加えるときに使われます。
この3つを組み合わせることで、シンプルながらもしっかりとした骨壷カバーが完成します。
初心者の方は、まず小さな練習布を編んで感覚をつかむことをおすすめします。
練習を繰り返すうちに、編み目のきつさやゆるさをコントロールできるようになります。
安定した編み目が作れるようになれば、骨壷カバーも自然ときれいに仕上がります。
焦らず丁寧に練習して、自信をつけてくださいね。
骨壷カバーを編む手順

骨壷カバーを編む手順を丁寧に解説します。
それでは一つずつ進めていきましょう。
底を編むステップ
骨壷カバーの底部分を編むことは、作品全体の基盤を作る大切な作業です。
まず、かぎ針編みの基本である「輪の作り目」を行います。
輪の中に細編みを6目ほど入れるのが基本で、そこから徐々に増し目をして底の直径を広げていきます。
増し目とは、同じ目に2回針を入れて編むことで、編地を大きくする方法です。
例えば、1段目は細編み6目、2段目は各目に2目ずつ編んで12目、3段目は「1目細編み+増し目」で18目といった具合に進めます。
このように段ごとに規則的に増し目をしていけば、きれいな円形の底が出来上がります。
骨壷の直径に合わせて増し目を調整し、底がぴったり収まるように作るのがポイントです。
途中で実際の骨壷を置いて確認しながら進めると、仕上がりのサイズがずれにくくなります。
底が小さすぎると入らなくなり、大きすぎると安定感がなくなるので注意してください。
本体を編むステップ
底が完成したら、次は骨壷カバーの本体部分を編んでいきます。
ここでは増し目をせずに、底の円周に沿って立ち上がるように編むのが基本です。
細編みでしっかりと編むと安定感があり、長編みを使うと模様が入りやすく柔らかい雰囲気になります。
高さは骨壷の肩まで、あるいはふたの下あたりまでを目安にします。
骨壷の形状によっては途中で編み方を切り替えたり、段ごとに模様を入れることでデザイン性を高めることもできます。
例えば「細編み2段+長編み1段」を繰り返すと、メリハリのある編地になります。
また、透かし模様を入れると涼しげな印象になり、編み目を詰めると落ち着いた雰囲気に仕上がります。
編んでいる途中で骨壷に合わせながら調整すると、フィット感が良くなります。
カバーは伸縮性があるので、ぴったりサイズを意識するのが成功のコツです。
縁の仕上げ方法
本体部分が編めたら、次は縁を仕上げていきます。
縁はそのままでも良いですが、ちょっとしたアレンジを加えると一気に完成度が高まります。
代表的な方法は「引き抜き編み」で縁を整えるやり方です。
引き抜き編みを一周すると、縁が引き締まり見た目もすっきりします。
また、ピコット編みを使えば縁に小さな飾りがつき、可愛らしい印象になります。
波模様の縁取りをするのも人気で、柔らかな印象を与える効果があります。
色を変えて縁取りをするだけでもアクセントになり、全体が引き立ちます。
縁の仕上げはシンプルでも良いですし、少し凝った編み方で華やかにするのも素敵です。
カバーの雰囲気や故人やペットのイメージに合わせて工夫してみてください。
ひもやリボンの付け方
最後に仕上げとして、ひもやリボンを付けてカバーを完成させます。
ひもは鎖編みで作るのが一般的で、必要な長さを編んだあと、本体の編み地に通して使います。
リボンを選ぶ場合は、サテンやオーガンジーのものが上品でおすすめです。
ひもやリボンを通す位置は本体の上部で、骨壷をしっかり固定できるようにします。
装飾の意味もありますが、実用性も兼ねているので丁寧に取り付けることが大切です。
ひもを絞ることで骨壷が安定し、カバーのズレを防ぐ効果があります。
また、リボンに小さなチャームや飾りを付ければ、よりオリジナリティのある作品になります。
シンプルに仕上げたい方は無地のリボンを、華やかにしたい方は柄入りや光沢のあるリボンを選ぶと良いでしょう。
この仕上げを工夫することで、世界に一つだけの骨壷カバーが完成します。
骨壷カバーを手編みするメリット
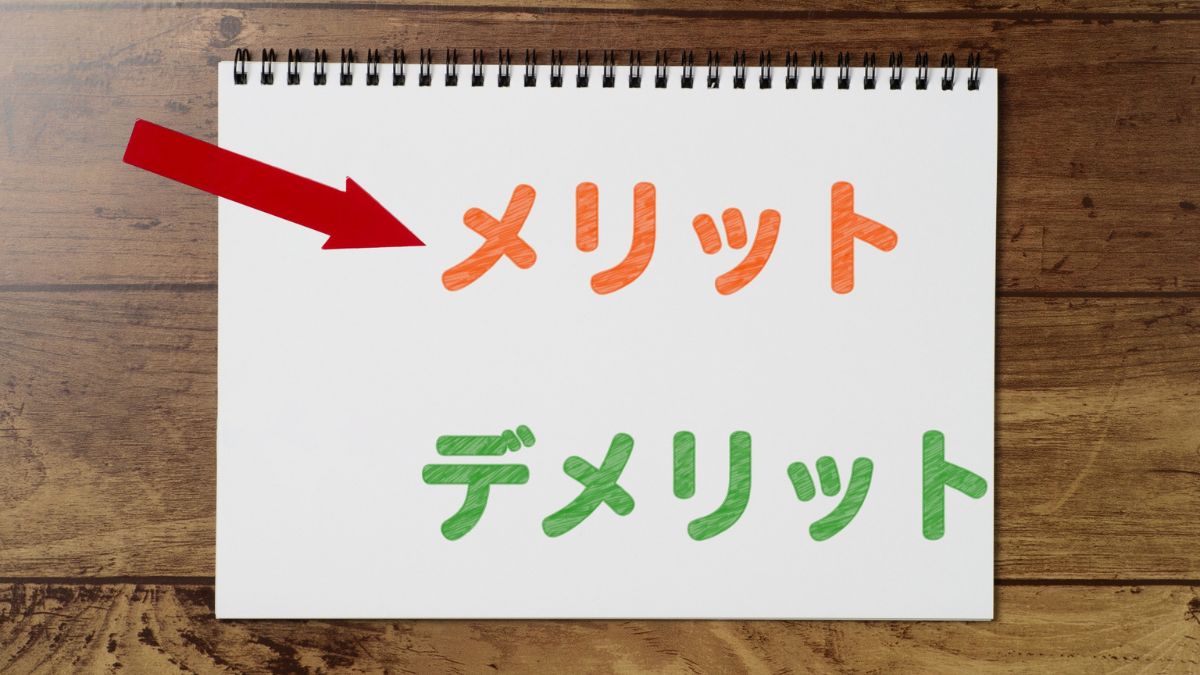
骨壷カバーを手編みするメリットについて解説します。
それでは順番に見ていきましょう。
世界に一つだけの温もり
骨壷カバーを手編みする最大の魅力は、世界に一つだけの温もりを感じられることです。
市販のカバーは既製品であるため、どうしても同じデザインや素材になりがちです。
しかし、手編みのカバーは一目一目に心が込められているため、唯一無二の存在になります。
同じ編み図を使っても、編み手の力加減や選んだ毛糸によって仕上がりが変わるのも特徴です。
この違いこそが「手作りならではの温もり」であり、大切な人やペットを包み込むのにふさわしい要素となります。
さらに、温もりは見た目だけでなく触り心地にも表れます。
手編みのカバーは柔らかく、やさしい手触りが骨壷に寄り添い、心を慰めてくれるのです。
手作りだからこその安心感
骨壷カバーを自分で編むことで得られる安心感も大きなメリットです。
大切な骨壷を守るものを自分の手で作ることで「自分がしっかり守ってあげられる」という感覚が生まれます。
既製品を買う場合、サイズが合わなかったり、素材が思っていたものと違ったりすることがあります。
その点、自分で編めば骨壷のサイズにぴったり合わせられるので、しっかりとした安心感があります。
また、壊れにくい丈夫な編み方を選んだり、毛糸の種類を工夫することで、実用性も高められます。
自分の手で作ることで、完成したときの達成感や「これで安心だ」という気持ちが強くなるのです。
色や模様を自由に選べる
色や模様を自由に選べることも、手編みならではの大きなメリットです。
例えば、故人が好きだった色や思い出の模様を取り入れることができます。
白やベージュなどの落ち着いた色を選べばシンプルで上品に仕上がり、明るい色を選べば華やかな印象になります。
また、模様編みや透かし編みを取り入れると、同じ毛糸でも表情が大きく変わります。
市販品ではなかなか見つからないデザインを、自分で実現できるのは手作りの強みです。
複数の色を組み合わせてボーダーにしたり、花のモチーフを加えることで、より個性的な作品に仕上げることも可能です。
世界観やイメージを自由に表現できるのは、手編みだからこそできる楽しみ方です。
故人やペットへの想いを込められる
最後に、骨壷カバーに想いを込められることは、何よりも大切なポイントです。
手を動かしながら編む時間は、自然と故人やペットを思い出す時間になります。
「ありがとう」という気持ちや「いつまでも一緒にいたい」という想いを糸に込めることができるのです。
既製品にはないこの時間こそが、手編みをする大きな意味といえます。
また、家族や友人と一緒に作れば、その過程も大切な思い出になります。
骨壷を包むカバーは、ただの布ではなく、心を込めたメッセージそのものになるのです。
この特別な気持ちが込められているからこそ、手編みの骨壷カバーには他にはない価値が宿ります。
骨壷カバーを編むときの注意点

骨壷カバーを編むときの注意点について解説します。
それでは一つずつ確認していきましょう。
サイズを正しく測る
骨壷カバーを編む際に最も重要なのが、サイズを正しく測ることです。
骨壷は直径や高さがメーカーや種類によって異なり、一般的なサイズでも数センチの違いがあります。
そのため、まずは自宅にある骨壷を実際に測り、底の直径、高さ、口の直径をメジャーで確認しましょう。
もし誤差が出てしまうと、カバーが入らなかったり、緩すぎてズレたりしてしまいます。
特に底のサイズは仕上がりに直結するため、編む途中でもこまめに骨壷をあてて確認することが大切です。
「少し大きめにして後で調整すればいい」という考え方ではなく、編み始めからぴったりを目指す方が成功しやすいです。
編み直しを防ぐためにも、事前のサイズ確認はしっかり行いましょう。
毛糸の耐久性に気を付ける
毛糸を選ぶときは、見た目や手触りだけでなく耐久性にも注意が必要です。
骨壷カバーは一度作ったら長期間使うことが多いため、毛羽立ちやすい糸や伸びやすい糸を使うと、早く劣化してしまいます。
特にアクリル毛糸は丈夫で扱いやすいため、耐久性を重視する場合におすすめです。
ウール毛糸は柔らかさが魅力ですが、湿気に弱い点があるため保管場所に注意が必要です。
また、安価な毛糸の中には毛玉ができやすいものもあるので、レビューや実際の質感を確認して選ぶと安心です。
長く大切に使うためには、素材の耐久性にこだわってください。
骨壷を保護するための工夫
骨壷カバーには見た目だけでなく、骨壷を保護する役割もあります。
陶器の骨壷は落としたりぶつけたりすると割れてしまうことがあるため、カバーで少しでも衝撃を和らげることが重要です。
細編みでしっかり編むと厚みが出て、衝撃吸収効果が高まります。
また、底部分は特に割れやすいため、二重に編んだり厚手に仕上げるのがおすすめです。
さらに、中に柔らかい布を一枚入れると、より安心感が増します。
デザイン性を意識することも大切ですが、安全性を優先した作りにすることで実用性がぐっと上がります。
湿気や汚れへの対策
湿気や汚れへの対策も忘れてはいけません。
毛糸製のカバーは湿気を吸いやすく、カビや臭いの原因になることがあります。
特に夏場や湿度の高い環境では注意が必要です。
カバーを編む際に、防虫・防湿効果のある毛糸を使うのも一つの方法です。
また、収納場所には乾燥剤を置くなどの工夫をすると安心です。
汚れについては、淡い色の毛糸は特にシミが目立ちやすいため、使う場所や扱い方を考慮して色を選びましょう。
日常的にホコリを払ったり、軽くブラッシングするだけでも清潔さを保てます。
湿気や汚れに強い工夫をしておくことで、長期間美しい状態を保てます。
骨壷カバーを手編みでアレンジする方法

骨壷カバーを手編みでアレンジする方法について解説します。
それでは順番に見ていきましょう。
刺繍で個性を加える
骨壷カバーに刺繍を加えると、シンプルな編み地が一気に特別感のあるデザインに変わります。
花やハート、イニシャルなど、思い出にまつわるモチーフを入れることで唯一無二の仕上がりになります。
刺繍は毛糸で編んだ後から刺す方法が一般的で、刺繍糸を使うと細かい模様を表現しやすいです。
例えば、故人が好きだった花を刺繍することで、その人らしさをカバーに込められます。
また、ペットの骨壷なら足跡や小さな骨の模様を入れると、とても可愛らしい雰囲気になります。
刺繍は小さなスペースから挑戦できるので、初心者にも取り入れやすいアレンジ方法です。
リボンやチャームで飾る
リボンやチャームを加えると、骨壷カバーが一層華やかになります。
サテンリボンをひも代わりに使うと上品に仕上がり、オーガンジーのリボンを結ぶと柔らかな印象になります。
また、小さなチャームをリボンに付ければ、より個性的で記念になるカバーになります。
チャームはクローバーやハート、星などシンプルなものが人気ですが、ペットなら肉球モチーフもおすすめです。
取り外し可能にしておけば気分によって変えられるので、季節ごとに違う飾りを楽しむこともできます。
シンプルな編み地も、リボンやチャームを加えるだけで印象ががらりと変わるので試してみると良いでしょう。
模様編みでデザイン性を出す
模様編みを取り入れると、骨壷カバーのデザイン性がぐっと高まります。
例えば、格子模様や透かし模様を取り入れると涼しげな雰囲気が出せます。
また、花のモチーフをつなぎ合わせてカバーに仕立てる方法もあり、とても華やかな仕上がりになります。
初心者の方は、ボーダー模様や交互に色を切り替えるだけでも簡単に個性を出せます。
かぎ針編みの魅力は、編み方次第で無限にデザインの幅が広がることです。
少しずつ練習しながら新しい模様に挑戦すると、編む楽しみも大きく広がります。
季節ごとの色合いを楽しむ
季節に合わせて色合いを変えるのも素敵なアレンジ方法です。
春ならパステルカラー、夏は涼しげなブルーやホワイト、秋はオレンジやブラウン、冬は赤やグリーンを取り入れると雰囲気が変わります。
同じ骨壷でも、季節やイベントに合わせてカバーを替えることで、暮らしの中に彩りが生まれます。
例えば、お盆や命日には特別な色合いのカバーを使うと、心を込めたお供えになります。
また、クリスマスや正月に合わせてアレンジするのも温かい思い出作りになります。
編み物の良いところは、糸を変えるだけで手軽に季節感を取り入れられる点です。
色を変えるだけで新しい雰囲気が楽しめるので、複数作って気分に合わせて使い分けるのもおすすめです。
まとめ|骨壷カバーの手編みでの作り方
| 骨壷カバーの手編みでの作り方 |
|---|
| 初心者に必要な材料 |
| 毛糸の選び方 |
| かぎ針のサイズと種類 |
| 基本的な編み目の使い方 |
骨壷カバーを手編みすることは、大切な人やペットを想いながら温もりを込められる特別な時間です。
市販品にはないオリジナリティや安心感を得られるだけでなく、色や模様を自由に選べるのも魅力です。
その一方で、サイズを正しく測ることや毛糸の耐久性に注意することも大切で、実用性と安全性を両立させる工夫が必要です。
刺繍やリボン、季節ごとのカラーを取り入れることで、カバーはより一層個性的で思いのこもったものになります。
手編みを通じて生まれる時間や作品は、故人やペットとの絆を深めてくれる大切な形になるでしょう。
参考リンク:初心者でもできる簡単骨壷カバーの手編み方法