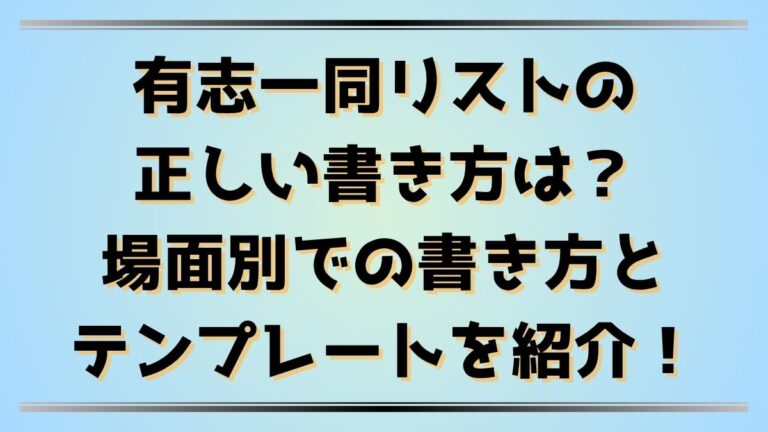有志一同リストの書き方に迷っていませんか。
退職祝い、結婚祝い、香典、供花など、さまざまな場面で使われる「有志一同」という言葉は、便利な反面、正しい書き方やマナーを知らないと失礼に見えてしまうことがあります。
この記事では、有志一同リストの正しい意味から、場面別の書き方、敬称の扱い方、WordやExcelでの作成方法まで、わかりやすく解説します。
ビジネスでもプライベートでも安心して使えるように、見やすく丁寧なリスト作成のコツを身につけましょう。
この記事を読めば、「これで間違いない」と自信を持って有志一同リストを作成できますよ。
有志一同リストの正しい書き方

有志一同リストの正しい書き方について解説します。
それでは順に詳しく見ていきましょう。
有志一同の正しい意味と使い方
「有志一同」とは、同じ目的や気持ちを持った複数人が自発的に集まったグループを意味します。つまり、組織や団体の正式な名義ではなく、あくまで「個人の意思で集まった人々」というニュアンスを持つ言葉です。
このため、社内であっても部署や課の名前を使わず、「〇〇部有志一同」「〇〇プロジェクト有志一同」といった表現にするのが自然です。たとえば、退職する上司に贈り物をする場合、「営業部有志一同」と記載すれば、部署の中の有志が行動しているという意味が伝わります。
一方で、「有志一同」はフォーマルな言葉としても十分に通用します。特に結婚祝いや香典、供花などでも使われるため、敬意を表しながらも控えめな表現として使われるのです。
ただし、「有志一同」は個人名を明記せずとも成立します。つまり、リストを添えなくても良いケースも多いのですが、相手に感謝を伝える目的がある場合や人数が限られている場合には、リストを添えることで誠意がより伝わります。
ビジネスでもプライベートでも、「有志一同」は“控えめな連名”として非常に便利な言葉です。
有志一同と連名の違いを理解する
「連名」とは、複数人が同じ目的で署名や贈り物を行う際に、全員の名前を記載する形式のことです。対して「有志一同」は、あえて個々の名前を出さずにグループとしてまとめる柔らかい表現になります。
たとえば、社内の送別会でプレゼントを渡す際、「営業部連名」とすると少し堅苦しい印象を与えますが、「営業部有志一同」とすることで、温かみと自発的な気持ちが感じられます。
また、結婚祝いや香典などで「連名」を使うと、受け取る側が全員の名前を把握できるメリットがありますが、人数が多い場合にはスペースの関係で見づらくなってしまいます。その場合には「有志一同」と記載し、別紙でリストを添える方法がスマートです。
フォーマル度の違いを整理すると、以下のようになります。
| 表現 | 意味・使い方 | 印象 |
|---|---|---|
| 連名 | 全員の氏名を明記する形式 | 正式・厳粛 |
| 有志一同 | 自発的な仲間の集まりを表す | 柔らかく丁寧 |
このように、「連名」は形式的で、「有志一同」は感情を込めた表現と覚えておくと良いでしょう。
リストを添えるときの基本ルール
有志一同のリストを添えるときには、いくつかのマナーがあります。まず、リストは必ず別紙にまとめるのが基本です。贈り物ののし紙や封筒には「有志一同」とだけ書き、詳細なメンバーは中のリストで伝えます。
リストの並び順は、原則として社内や組織の場合は役職順にします。上司や年長者を上に、同格のメンバーは五十音順にまとめると見やすくなります。プライベートな集まりでは、特に序列をつけず五十音順で統一するのが良いでしょう。
また、敬称(様・さん)は基本的に不要です。「営業部有志一同」リスト内に「山田太郎」「佐藤花子」といった形で氏名だけを並べることで、すっきりとした印象になります。どうしても敬意を表したい場合は、全員に「様」を付けるなど統一感を大切にします。
人数が多い場合は、「代表者名+他〇名」とまとめる表記も可能です。例:「山田太郎 他12名(営業部有志一同)」のように書くと、シンプルかつ伝わりやすくなります。
いずれの場合も、リストは見やすく整列させ、フォントや余白を統一すると丁寧な印象を与えられます。
敬称や順序をつけるときの注意点
敬称や順序をつけるときには、立場や関係性を踏まえて丁寧に判断する必要があります。特に社内の上司を含む場合や、取引先へ渡す場合には注意が必要です。
基本的には、役職が高い人ほど上位に記載します。たとえば、「部長→課長→主任→一般社員」という順です。肩書きを書く場合は「営業部 部長 山田太郎」のように、氏名の前に役職を入れます。
ただし、社外やプライベートなシーンでは、役職を省略しても問題ありません。その場合は五十音順にするか、プロジェクト名やチーム名でまとめて表現します。
また、「様」「さん」を混在させると失礼な印象を与えるため、敬称を付ける場合は全員統一することが大切です。誰か一人だけ「様」を外すのはNGです。
さらに、人数が多い場合には、「代表者名+他有志一同」とするのが最も無難で上品です。シンプルでありながらも、感謝の気持ちをしっかり伝えることができます。
有志一同リストを添えるべき場面と書き方の例

有志一同リストを添えるべき場面と書き方の例を紹介します。
場面によって、リストの書き方や添え方のマナーが変わります。順に見ていきましょう。
退職祝いでのリストの書き方
退職祝いでは「有志一同」が最もよく使われる場面です。部署内の仲間や同僚が集まってプレゼントを贈るとき、「営業部有志一同」「開発チーム有志一同」といった形でまとめるのが一般的です。
退職祝いでは、贈り物や花束に添えるのし紙に「祝定年退職」「御礼」などの表書きを入れ、下段に「営業部有志一同」と記載します。メッセージカードを添える場合には、本文の最後に「営業部有志一同より」と一文を添えるとより丁寧です。
リストを添える場合は、贈り物とは別にカードやA4用紙などにまとめましょう。書き方の例は次の通りです。
| 部署名 | 名前の並び | 備考 |
|---|---|---|
| 営業部有志一同 | 部長→課長→一般社員の順 | 敬称は省略 |
たとえば、以下のように記載します。
営業部有志一同
部長 山田太郎
課長 佐藤健
主任 鈴木花子
一般社員 田中陽介
退職者が複数部署に関わっている場合は、「営業部・企画部有志一同」と連名にしても構いません。その場合は、リストを「部署ごと」に区切ると読みやすくなります。
結婚祝いでのリストの書き方
結婚祝いで「有志一同」を使う場合は、職場や友人グループなどで共同でお祝いを贈るときに便利です。お祝い金やプレゼントにのし紙をつけるときは、「寿」「御結婚御祝」などの表書きを使い、下段に「〇〇部有志一同」と記載します。
リストは必ず別紙にして同封しますが、華やかな場面なので、ピンクや淡い色の紙を使うと温かみが出ます。Wordで作成する場合は、フォントを明朝体にして整えると上品です。
名前の順番は職場関係なら役職順、友人グループなら五十音順で問題ありません。肩書きを書く場合は略称を使いましょう。
たとえば、「情報システム部有志一同」の例では次のようになります。
情報システム部有志一同
部長 山本大輔
課長 木村真一
係長 高橋優
主任 中村明
このように、結婚祝いでは丁寧さと温かみを両立することが大切です。無理に肩書きを書かなくても、全員の気持ちが伝わるようなレイアウトを意識しましょう。
香典や供花でのリストの書き方
香典や供花では、「有志一同」という表現が特に多く使われます。故人との関係を大切にしつつ、目立ちすぎない上品な印象を与えるためです。
香典袋の表書きは「御香典」「御霊前」などとし、下段に「営業部有志一同」「同期有志一同」などを記載します。個人名は袋に直接書かず、リストとして別紙にまとめて封入します。
リストの順番は役職順が基本ですが、弔事の場合は上下関係を強調しすぎない方が良いとされます。そのため、五十音順で統一するのも丁寧な方法です。
リストの紙は白無地の用紙を使い、派手な色は避けましょう。フォントはゴシック体よりも明朝体が適しています。次のように書きます。
営業部有志一同
部長 山田太郎
課長 佐藤健
係長 鈴木花子
社員 田中陽介
供花の場合は、札の下段に「営業部有志一同」とのみ書き、リストは葬儀社に提出する形式で別途添えます。人数が多い場合は「代表者名+他有志一同」で問題ありません。
社内プロジェクトや寄付でのリストの書き方
社内プロジェクトでの表彰や寄付活動などでも「有志一同」のリストを使う場面があります。特に募金活動やボランティアで使う場合、寄付金に添付する名簿や報告書に「有志一同」と記載することで、全体の統一感を出せます。
この場合のリストは、参加者全員の名前を正確に書きます。金額を明記する場合は、金額順や五十音順など統一した並び順にします。以下は例です。
| 氏名 | 所属 | 金額 |
|---|---|---|
| 山田太郎 | 営業部 | 5,000円 |
| 佐藤花子 | 企画部 | 5,000円 |
| 鈴木健 | 総務部 | 3,000円 |
提出書類や報告書の末尾には、「〇〇有志一同」と記載し、代表者の名前と押印を添えるのが丁寧です。たとえば、「環境活動支援プロジェクト有志一同 代表 山田太郎」と記載します。
寄付や社内活動における「有志一同」は、形式よりも誠意を大切にする表現です。整ったリストは、責任感と信頼を伝える大切な要素になります。
有志一同リストを見やすく作るポイント

有志一同リストを見やすく作るポイントを紹介します。
リストは単に名前を並べるだけではなく、見やすく丁寧に整えることが大切です。相手に誠意を伝えるための「デザイン」と考えましょう。
WordやExcelでのレイアウトの整え方
WordやExcelを使えば、有志一同リストをきれいに整えることができます。まず、Wordを使う場合は「表機能」を利用して、氏名・所属・役職などの欄を作成しましょう。余白を広めに取り、文字サイズは10.5~12ポイントが見やすいです。
氏名は中央揃えにすると整った印象になります。Wordのレイアウトでよく使われる設定は以下の通りです。
| 項目 | 推奨設定 |
|---|---|
| フォント | MS明朝 または 游明朝 |
| 文字サイズ | 10.5〜12pt |
| 行間 | 1.3〜1.5倍 |
| 余白 | 上下20mm・左右25mm |
Excelで作る場合は、罫線を利用して簡単に名簿表が作れます。1行目に見出しを付け、「氏名」「所属」「役職」「備考」といった項目を入力しましょう。列幅を均等に設定し、中央揃えで整えると見栄えが良くなります。
Wordは文書形式、Excelは表形式に強いため、人数が少ない場合はWord、多い場合はExcelで作成するとバランスが取れます。
人数が多いときの省略の仕方
有志一同リストは人数が多いほど見づらくなる傾向があります。そのため、参加人数が10名を超える場合には「代表者名+他〇名」とするのが一般的です。
たとえば、「山田太郎 他15名(営業部有志一同)」とすれば、全体を簡潔に表現できます。別紙で全員の名簿を添える場合は、フォーマルな書式で整えましょう。
人数がさらに多い場合には、部署単位でまとめる方法もおすすめです。次のように構成します。
営業部有志一同(代表 山田太郎 他12名)
企画部有志一同(代表 佐藤花子 他9名)
また、学校や地域団体の場合は、「〇〇有志一同(参加者一覧は別紙参照)」とする書き方も自然です。相手にとって見やすく、誰が関わったかをきちんと伝えられる形を意識しましょう。
全員の名前を書く場合には、段組みを使って2列や3列に分けると、スペースを節約しながら整った印象を与えられます。
手書きと印刷のどちらがよいか
「有志一同リスト」は、フォーマル度や人数によって手書きか印刷かを選びましょう。少人数の場合は手書きでも温かみがあり、丁寧な印象を与えます。一方で人数が多い場合やビジネスシーンでは、印刷が推奨されます。
手書きで作る場合は、筆ペンや黒ボールペンを使用します。鉛筆やフリクションペンは避けましょう。字の大きさをそろえ、行を一定間隔に保つことが大切です。
印刷の場合は、フォント選びに気をつけましょう。明朝体はフォーマル、ゴシック体はカジュアルな印象になります。WordやExcelで印刷する場合は、白い上質紙または厚めのA4用紙を選ぶと丁寧な印象に仕上がります。
ただし、印刷であっても署名欄だけ手書きにする方法もあります。この組み合わせは、フォーマルさと温かみを両立できるためおすすめです。
手書きでも印刷でも、「整っていること」が最も重要です。乱雑な印象を与えないように意識しましょう。
署名欄を作るときのコツ
署名欄を作るときは、全員が記入しやすいように余白を広く取りましょう。A4横向きにして3列〜4列の枠を設けると、複数人でもスムーズに署名できます。
署名欄の上部には「署名欄」や「参加者名」といったタイトルを入れ、各行に罫線を引いておくときれいに見えます。次のような構成が便利です。
| 署名欄フォーマット例 |
|---|
| 【署名欄】 _______________ _______________ _______________ _______________ |
また、署名欄の下部に「以上〇〇有志一同」と入れることで、リスト全体が締まります。手書きで署名を集める場合は、筆圧や筆跡の違いも個性として残るため、温かみのある印象になります。
デジタルで署名を集める場合は、ExcelやPDFを共有し、入力後に印刷する方法も有効です。特にオンライン環境が増えた今は、手書きとデジタルの併用が主流になりつつあります。
署名欄の目的は「一体感の見える化」です。見た目の整え方ひとつで、贈り物や文書全体の印象が大きく変わります。
有志一同の表記に関するマナー

有志一同の表記に関するマナーについて詳しく解説します。
「有志一同」という言葉は便利でありながらも、扱い方を誤ると相手に失礼な印象を与えることがあります。ここでは、使う位置や順序、敬称の付け方などを正しく理解しておきましょう。
有志一同の位置や書く順番のルール
「有志一同」は、贈り物やのし紙、メッセージカードなどに記載する位置によって印象が変わります。最も基本的なルールは、「のし紙や表書きの下段中央」に書くということです。
たとえば、退職祝いの場合は、上段に「御礼」や「感謝」を書き、下段の中央に「営業部有志一同」と入れます。この位置に書くことで、正式かつ丁寧な印象になります。
メッセージカードに書く場合は、本文の最後に「営業部有志一同より」または「〇〇プロジェクト有志一同」と入れるのが自然です。本文の途中や冒頭に書くと、不自然に見えるため注意しましょう。
また、リストを別紙で添える場合は、本文中に「(参加者一覧は別紙参照)」と補足を入れておくと親切です。受け取る相手にとって読みやすく、誰が関わったのかが一目で分かる構成が理想です。
表記の順番としては、「部署名(グループ名)+有志一同」の順に書くのが基本です。「有志一同営業部」とすると意味が変わるため誤りです。
間違えやすい敬称や肩書の扱い方
「有志一同」のリストにおける敬称や肩書の扱いは、シーンによって異なります。ビジネスの場合は、基本的に「役職+氏名」で統一し、敬称は省略するのが一般的です。たとえば、「部長 山田太郎」「課長 佐藤健」のように記載します。
友人同士や地域活動の場合は、肩書きを省いて五十音順で並べると柔らかい印象になります。この場合、敬称を付けるかどうかは統一を意識してください。「様」「さん」が混在するのは失礼にあたります。
特に気をつけたいのが、代表者名を記載する場合です。「代表 山田太郎 他営業部有志一同」とするのが自然ですが、「代表営業部 山田太郎」のように書くのは誤りです。代表は「有志一同」を修飾する立場であり、グループ名の後に書くのが正しい形です。
肩書を長く書きすぎると全体が読みにくくなるため、部署名は省略しても問題ありません。大切なのは、全員の表記を揃えることです。
また、社外の方へ贈る場合や弔事では、相手の肩書や敬称は省略し、自分たちのリストにのみ役職を記すのがマナーです。
誤解を招く書き方の例
「有志一同」は便利な表現ですが、書き方によっては誤解を招くことがあります。たとえば、「〇〇部一同」と「〇〇部有志一同」では意味が異なります。
「〇〇部一同」は、その部署全員が関与していることを意味します。一方で「〇〇部有志一同」は、その中の一部のメンバーが自発的に参加していることを示します。この違いを理解せずに使うと、他の人が関わっていないのに誤解されることがあります。
また、「有志一同御中」や「有志一同様」と書くのも誤りです。「有志一同」は団体名であって、宛名ではないため、敬称を付ける必要はありません。
さらに、文末に「有志一同から」や「有志一同です」と書くのも避けましょう。正しくは「有志一同より」とすることで、丁寧な印象になります。
特に公的文書や会社間の贈答では、形式的な部分が評価に影響するため、慎重に記載しましょう。
フォーマルとカジュアルの違いを意識する
「有志一同」は場面によってフォーマルにもカジュアルにも使える表現です。使い方を誤ると、意図せず堅すぎたり軽すぎたりしてしまいます。場面ごとのトーンを意識して使い分けることが大切です。
フォーマルな場(退職・弔事・公的表彰など)では、明朝体や縦書きを基本とし、シンプルで整った構成を意識します。紙質も白無地や上質紙を使い、余白を広めに取ることで落ち着いた印象を与えられます。
一方で、カジュアルな場(結婚・出産・誕生日など)では、ゴシック体や横書き、柔らかい色合いの紙でも構いません。メッセージカードにイラストを添えるのも好印象です。
また、弔事では黒インクを使用し、祝事では黒または濃いグレーを使うなど、色のマナーも意識しましょう。特にカラー印刷は、カジュアルな印象が強くなるためフォーマルな場面では避けた方が無難です。
フォーマルとカジュアルを正しく使い分けることで、相手に対して誠意と品格の両方を伝えることができます。
シーン別の有志一同リストのテンプレート集

シーン別の有志一同リストのテンプレート集を紹介します。
ここでは、Wordや手書きでそのまま使える「有志一同リスト」のテンプレートを紹介します。目的に応じて、文面やレイアウトをアレンジしてください。
ビジネス文書用テンプレート例
ビジネスシーンでは、退職・転勤・表彰・寄付などのフォーマルな文書に添える形で「有志一同リスト」を使用します。整った書式で作ることが大切です。
以下はWordで作成できるテンプレート例です。
| 営業部有志一同リスト | |
|---|---|
| 役職 | 氏名 |
| 部長 | 山田太郎 |
| 課長 | 佐藤健 |
| 主任 | 鈴木花子 |
| 一般 | 田中陽介 |
このテンプレートは、社内文書として上司や取引先へ渡す際に使いやすい形式です。タイトルには部署名+有志一同を明記し、全員の役職と氏名を整列させるのが基本です。
人数が多い場合は「代表者名+他〇名」として省略できます。リストの下には「以上、営業部有志一同」と締めの一文を添えると、文書全体の印象が整います。
結婚やお祝いカード用テンプレート例
結婚や出産などのお祝いでは、明るく温かみのあるデザインを意識しましょう。Wordや手書きカードで簡単に作れるテンプレートを紹介します。
【テンプレート例】
情報システム部有志一同
部長 山本大輔
課長 木村真一
係長 高橋優
主任 中村明
社員 佐々木彩
メッセージカードの場合は、リストの上部に「Congratulations!」や「お幸せをお祈りします」などの一言を入れると華やかになります。
背景に淡いピンクや水色の罫線を入れると、やわらかく親しみのある印象を与えられます。フォントは明朝体でもゴシック体でも構いませんが、文字サイズは11pt前後が読みやすいです。
Wordで作成する場合は、ページ罫線を使って枠を付けるとより上品に見えます。フォントカラーを黒またはグレーで統一するのが無難です。
弔事や供花用テンプレート例
弔事用の「有志一同リスト」は、最も慎重に扱う必要があります。控えめなデザインと、心を込めた表現を意識しましょう。
【テンプレート例】
営業部有志一同
部長 山田太郎
課長 佐藤健
係長 鈴木花子
社員 田中陽介
フォントは必ず黒色で、明朝体を使用します。ゴシック体やカラー文字は不適切です。紙は白無地の上質紙を使用し、装飾は一切不要です。
供花の場合は、札の下段に「営業部有志一同」とのみ記載し、リストは別途A4用紙にまとめて葬儀社や遺族側に提出します。
また、リスト内で「敬称」を付けないのが一般的です。肩書きを入れる場合も簡潔にし、整然とした配置を意識してください。
学校や地域活動で使えるテンプレート例
学校や地域活動などのカジュアルな場では、柔らかく親しみやすいデザインを心がけます。特にPTAやクラブ活動などで使用する場合、リストには所属や学年を入れるとわかりやすくなります。
【テンプレート例】
| 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|
| 田中花子 | PTA有志一同 | 代表 |
| 鈴木一郎 | PTA有志一同 | 副代表 |
| 中村亮 | PTA有志一同 | メンバー |
カラー印刷も問題ありませんが、過度な装飾は避けましょう。手書きの場合は、黒または濃い青のペンを使用します。
地域活動やクラブでは、署名欄を設ける形式も人気です。全員が署名をすると、団結感や温かみが伝わります。
テンプレートを使う際は、フォーマットにこだわるよりも「誰が関わっているか」をわかりやすく伝えることを意識しましょう。誠実さが伝わるシンプルなデザインが一番です。
まとめ|有志一同リストの書き方
| 記事内の主要項目リンク |
|---|
| 有志一同の正しい意味と使い方 |
| 退職祝いでのリストの書き方 |
| WordやExcelでのレイアウトの整え方 |
| 有志一同の位置や書く順番のルール |
| ビジネス文書用テンプレート例 |
有志一同リストを書くときは、「誰が」「どんな気持ちで」参加しているかを正確に伝えることが大切です。
のし紙やカードでは下段中央に「〇〇有志一同」と書き、リストは別紙で添えるのが基本です。
ビジネスでは役職順、プライベートでは五十音順で整えると見やすく、敬称は付けないのが一般的です。
人数が多い場合は「代表者名+他〇名」と省略し、WordやExcelを使えば簡単に整ったリストを作成できます。
フォーマルな場では控えめに、カジュアルな場では温かみを添えて。相手に誠意を伝える一枚を意識しましょう。
正式な文書表記のルールについては、文化庁の公式ページ「文化庁公式サイト」も参考になります。