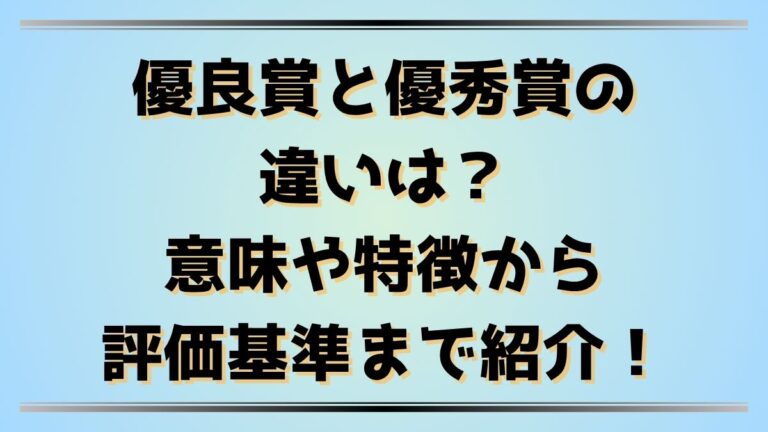「優良賞と優秀賞って、どっちが上なんだろう?」
コンクールや学校の表彰でよく聞くこの2つの賞、似ているようで実は意味も順位も少し違います。
この記事では、優良賞と優秀賞の違いをわかりやすく解説し、それぞれがどんな基準で評価されるのかを紹介します。
さらに、受賞したときの価値や履歴書への書き方、就職活動での活かし方まで詳しくまとめました。
これを読めば、自分やお子さんの受賞がどんな意味を持つのか、しっかり理解できます。
受賞経験を次のステップにつなげたい方にも、きっと役立ちますよ。
優良賞と優秀賞の違いをわかりやすく解説

優良賞と優秀賞の違いをわかりやすく解説します。
それでは、詳しく見ていきましょう。
優良賞と優秀賞の基本的な意味
優良賞と優秀賞は、どちらも「高い評価を受けた作品」に与えられる賞ですが、意味合いには明確な違いがあります。
優良賞は「基準を十分に満たした良い作品」に贈られる賞であり、安定した完成度や確実な努力が認められる位置づけです。
一方で、優秀賞は「特に優れている」と評価された作品に贈られる賞で、独創性や完成度の高さ、他にない発想が重視されます。
つまり、優良賞が「合格ラインを超えた優れた作品」なのに対し、優秀賞は「その中でも際立った作品」に与えられるという違いがあります。
学校や企業の表彰式でも、この2つの賞はよく並びますが、優秀賞の方が一段上位に位置づけられるのが一般的です。
評価基準の違い
優良賞と優秀賞では、審査員が重視するポイントが異なります。
優良賞の場合、「基礎力の高さ」「安定した仕上がり」「バランスの良さ」が重視されます。
特にコンクールや作文大会などでは、誰が見ても安心して評価できる作品が優良賞として選ばれる傾向があります。
優秀賞はそれに対して、「独創性」「表現力」「完成度」が評価の中心です。
たとえば、絵画コンクールでは優良賞が「正確で丁寧に描かれた作品」なら、優秀賞は「独特の世界観や強いメッセージ性を持つ作品」といった違いになります。
順位の違いと扱われ方
順位で言うと、優良賞よりも優秀賞の方が上位に位置します。
一般的な序列としては、「入選 → 優良賞 → 優秀賞 → 金賞(または最優秀賞)」という順番で設定されることが多いです。
ただし、これは主催団体によって異なり、必ずしも全国共通ではありません。
とはいえ、評価の段階を表す目安として、優秀賞がより高い評価であることは間違いありません。
この違いを知っておくと、結果発表の際に自分の立ち位置を正しく理解しやすくなります。
よくある誤解と正しい理解
よく「優良賞のほうが“良い”という言葉があるから上なんじゃないの?」と誤解されますが、実際は逆です。
「優良」は“良い状態を保っている”という意味であり、「優秀」は“他よりも優れている”という意味を持ちます。
つまり、言葉の成り立ちから見ても、優秀賞の方が上位になります。
また、どちらの賞も価値があることに変わりはなく、評価されるポイントが違うだけです。
努力や継続性が評価されるのが優良賞、独創性や結果が評価されるのが優秀賞と考えると理解しやすいですね。
優良賞の意味と特徴

優良賞の意味と特徴を詳しく紹介します。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
評価されるポイント
優良賞は「安定して良い結果を出した作品」に贈られることが多いです。
つまり、極端に目立つ要素がなくても、全体的な完成度が高く、基本がしっかりしていることが大切なんですね。
たとえば、作文コンクールであれば構成が整っていて、文法ミスが少なく、読みやすい文章が評価されます。
絵画コンテストなら、色使いのバランスやテーマの理解度が高く、見る人に「丁寧に作られた作品だな」と感じさせるものが選ばれます。
つまり、優良賞は“突出した作品”というよりも、“安心して推薦できる優れた作品”という印象なんです。
学校やコンクールでの位置づけ
学校やコンクールでは、優良賞は「上位には届かないけれど、確かな評価を得た作品」に与えられることが多いです。
入選や佳作よりも上位に位置するため、全体の中でもかなり評価が高い部類に入ります。
たとえば吹奏楽コンクールでは、優良賞を取った学校は「安定した演奏ができた」「全体の完成度が高い」といったコメントを受けることが多いです。
逆に、挑戦的なアプローチをしたけれど、少し粗が目立った場合などは、優秀賞や金賞には届かないことがあります。
このように、優良賞は“基礎力が評価された証”であり、非常に価値のある賞なんです。
優良賞に選ばれやすい作品の傾向
優良賞を受ける作品にはいくつかの共通点があります。
まず、「丁寧さ」があること。これはどのジャンルでも共通する要素です。
作文なら文の流れが自然で、誤字脱字がなく、読みやすい。
絵画なら、色彩の統一感や線の正確さがあり、全体として完成度が高い。
音楽や演技なら、テンポや表現力に安定感があることが重要です。
もうひとつの特徴は、「ルールやテーマをしっかり守っている」ことです。
審査基準に忠実な作品は評価が安定しやすく、結果的に優良賞につながることが多いです。
逆に、独自性や奇抜さを出しすぎると、完成度が下がってしまうケースもあります。
そのため、バランスを重視する姿勢が大切なんです。
優良賞を取るためのコツ
優良賞を狙うには、「正確さ」「丁寧さ」「全体の統一感」を意識することが一番大切です。
極端に個性を出すよりも、基礎をしっかり固めることが重要なんですね。
例えば作文であれば、書き出しから結論までの流れを明確にし、文体を整えること。
絵画であれば、構図のバランスを確認し、仕上げの段階で細部まで丁寧に描くこと。
そしてもう一つ大事なのが「テーマ理解」です。
審査員が「このテーマをよく理解しているな」と感じる作品は、それだけで印象が良くなります。
優良賞は、努力と誠実さを評価される賞です。
派手さがなくても、着実に仕上げた作品が報われるのが、この賞の魅力なんですよ。
優秀賞の意味と特徴
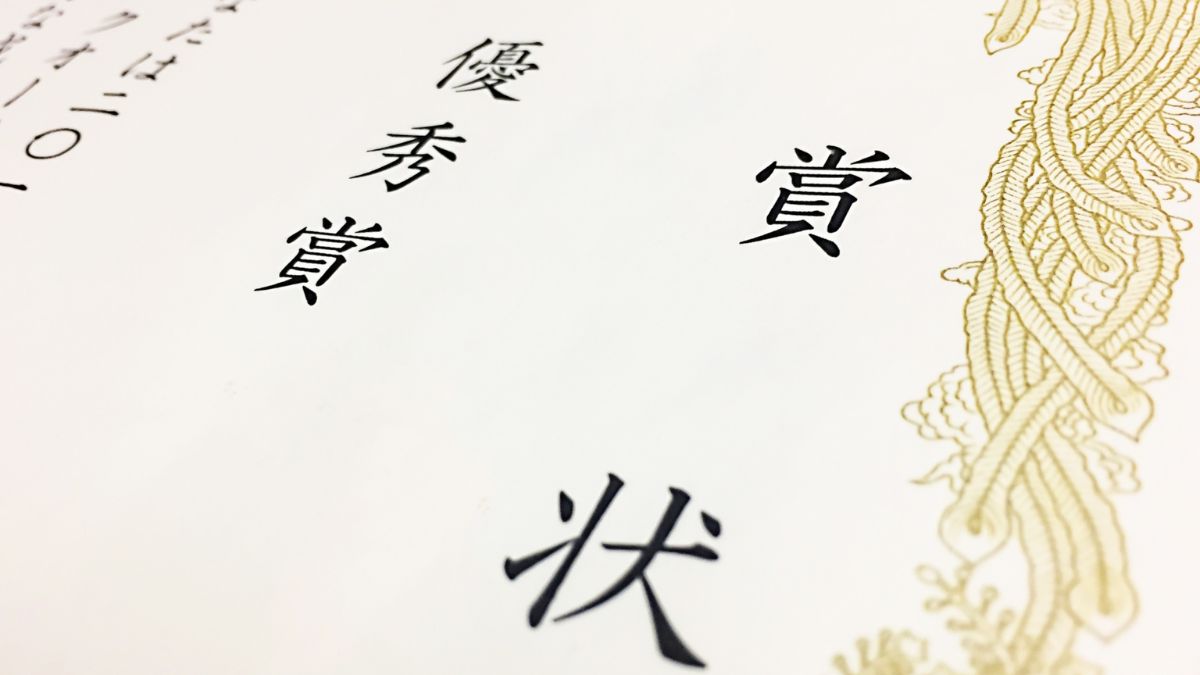
優秀賞の意味と特徴を解説します。
それでは順番に見ていきましょう。
優秀賞が評価される理由
優秀賞は、数ある応募作品の中でも「特に優れている」と評価された作品に与えられる賞です。
優良賞よりも一段階上の評価となり、独自性や完成度の高さが特に重視されます。
審査員から見ると、「この作品には他と違う魅力がある」「印象に残る」という感覚を持たせることが大切なんですね。
また、優秀賞は単に上手いだけではなく、「伝えたいことがしっかり伝わっているか」「テーマを深く理解しているか」など、作品に込めた意図も評価対象になります。
つまり、技術と表現力、そして感性の三つが揃って初めて優秀賞に届くということです。
独創性や完成度の重要性
優秀賞の大きな特徴は、独創性と完成度のバランスが取れていることです。
ただ新しいことをやるだけではなく、それをきちんと形にして完成させる力が必要になります。
たとえば、絵画コンクールで優秀賞を取る作品は、構図がユニークでありながら、色使いや技術面でも高水準です。
作文なら、自分の体験や考えを独自の視点で書きながらも、読みやすく整理された構成がポイントになります。
つまり、優秀賞は“チャレンジと完成度の両立”を評価する賞なんです。
審査員は「挑戦しているけれど破綻していない」「個性がありながらも丁寧に仕上げている」作品に強く惹かれます。
そのため、作品作りの段階で“見せたいポイント”を明確にしておくことが重要です。
優秀賞に選ばれる作品の共通点
優秀賞に選ばれる作品には、いくつかの共通する特徴があります。
まずひとつは、「テーマの理解が深い」ことです。
テーマを表面的に捉えるのではなく、掘り下げて考え、自分の言葉で表現している作品が高く評価されます。
次に、「表現に一貫性がある」ことも重要です。
文章や構図、色使い、演出の方向性などがぶれず、全体としてメッセージが明確であることが評価されます。
さらに、「他の作品にはない印象を残す」ことも共通点のひとつです。
それは派手な演出ではなく、たとえば静かだけれど心に響く描写や、深い感情が伝わる構成など、人を惹きつける“余韻”を持っていることが多いです。
このような作品は、審査員の記憶に残りやすく、結果として優秀賞に選ばれやすくなるのです。
優秀賞を目指すためのポイント
優秀賞を目指すためには、まず“自分らしさ”を作品に反映させることが大切です。
他の人と同じような内容では、どうしても印象に残りにくいですからね。
ただし、個性を出すときには「伝わるかどうか」を意識する必要があります。
独創的な表現であっても、伝わらなければ評価されません。
ですから、表現の工夫とともに、見る人・読む人の立場を意識して構成することが大切です。
また、技術面を磨くことも忘れてはいけません。
独創性があっても、仕上げが雑だと評価は下がります。
そのため、提出前に細部を見直したり、第三者に意見をもらうなど、完成度を高める努力が欠かせません。
このように、優秀賞を取るには「独自の視点」「完成度」「伝わりやすさ」という三つの軸を意識して作品を作るのがコツです。
この三つが揃えば、自然と審査員の目に留まる作品になりますよ。
優良賞と優秀賞の順位

優良賞と優秀賞の順位について解説します。
それでは、詳しく見ていきましょう。
どちらが上位か
結論から言うと、優秀賞の方が優良賞よりも上位に位置します。
一般的な順位としては、「入選 → 優良賞 → 優秀賞 → 金賞(または最優秀賞)」という並びです。
優良賞は“十分に良い”と認められた作品、優秀賞は“特に優れている”と判断された作品という違いがあります。
つまり、どちらも高評価ですが、優秀賞はその中でも一歩抜きん出た成果を示しているということです。
ただし、主催団体やコンテストによっては名称や順番が異なる場合もあります。
しかし、評価のニュアンスとしては、ほとんどの場合で優秀賞が上位になります。
金賞や特選賞との違い
優秀賞のさらに上に位置するのが「金賞」や「特選賞」です。
これらの賞は、審査員全員が満場一致で「これは特別に素晴らしい」と認めた作品に授与されることが多いです。
優秀賞が「とても良い作品」なら、金賞や特選賞は「その年を代表する最高の作品」と言えるレベルです。
たとえば吹奏楽コンクールの場合、金賞は全国大会出場レベルの団体に与えられることが多く、審査員から見ても非の打ち所がない完成度を示しています。
一方、優秀賞は惜しくも最高位には届かないものの、非常に高い完成度を持った作品や演奏に授与されます。
優良賞は安定感、優秀賞は独創性と完成度、金賞は圧倒的な完成度と表現力が評価の基準になるわけです。
この3つを比べることで、自分の作品の位置づけや今後の目標も明確にできます。
審査員の視点から見る評価基準
審査員は、優良賞と優秀賞を分けるときに「何を見ているのか?」という点を知ると理解が深まります。
優良賞では、基本的な完成度・技術・テーマ理解がしっかりしているかが評価の中心です。
一方、優秀賞では、そこに“作品の個性”や“感動を与える力”が加わっているかどうかが判断基準になります。
たとえば作文であれば、文章が正しく書けているだけでなく、読み手の心を動かす表現があるかどうか。
絵画なら、構図や色彩のバランスに加えて、作品全体から伝わる雰囲気や感情が重視されます。
つまり、優秀賞は「技術を超えた感性の評価」でもあるんです。
審査員の多くは、評価表のコメントで「印象に残る」「表現に深みがある」といった言葉を添えることが多いです。
このことからも、優秀賞が“感動を与える力”を重視していることがわかります。
受賞後に変わる評価と影響
優良賞や優秀賞を受賞すると、その後の評価やモチベーションに大きな違いが生まれます。
まず、学校や教育現場では、優秀賞は内申点や評価欄にプラスの影響を与えることがあります。
特に作文や研究発表などでは、受賞経験が進学や推薦の際に評価されることもあります。
優良賞ももちろん価値が高く、努力と継続力が証明される賞として扱われます。
履歴書や自己PRで書く際には、「優良賞受賞(安定した成果を評価)」などのように説明を添えると印象が良くなります。
一方、優秀賞は「高い完成度と独自性を評価されて受賞」と記載でき、より強いアピールにつながります。
また、受賞後にモチベーションが上がり、次の挑戦に前向きになる人も多いです。
特に子どもや学生にとっては、「次は金賞を目指したい」という明確な目標が生まれるきっかけになります。
このように、受賞の順位は単なる“上下”ではなく、次のステップへ進む“道しるべ”になるんです。
優良賞と優秀賞の履歴書での書き方

優良賞と優秀賞の履歴書での書き方を解説します。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
どのように記載するのが正しいか
履歴書やエントリーシートに受賞歴を書く場合は、正式な名称で記載することが大切です。
たとえば、「〇〇コンクール 優秀賞受賞」「△△コンテスト 優良賞受賞」といった書き方が基本です。
主催団体名がわかる場合は、より信頼性が増すので「〇〇主催 △△コンクール 優秀賞受賞」と記載するのがベストです。
また、受賞した時期も可能であれば添えると、応募者の成長や継続性が伝わります。
履歴書に書く際は、学歴や職歴の下の「賞罰欄」または「自己PR欄」に記入します。
正式なフォーマットでまとめることで、誤解なく伝わり、印象も良くなります。
| 正しい書き方の例 | ポイント |
|---|---|
| 〇〇市読書感想文コンクール 優秀賞受賞 | 正式名称を記載する |
| △△美術展 優良賞受賞(〇〇主催) | 主催団体名を加えると信頼度アップ |
| □□音楽コンクール 優秀賞(2023年度) | 受賞年があると活動時期が伝わる |
就職活動での印象の違い
優良賞と優秀賞は、どちらも高い評価を受けた証ですが、印象には微妙な差があります。
優秀賞は「特に優れた成果を上げた」「他と差をつけた努力を評価された」という印象を与えます。
そのため、企業の採用担当者からは「高い完成度を発揮できる人」「創造性がある人」と受け取られることが多いです。
一方、優良賞は「安定して良い結果を出せる」「基本を丁寧に積み重ねられる人」というイメージにつながります。
つまり、優良賞は“誠実さ”や“努力の継続性”、優秀賞は“結果を出す力”や“独創性”を象徴しているのです。
どちらも評価ポイントは異なりますが、どちらもポジティブな印象につながります。
自己PRへのつなげ方
受賞歴を自己PRに活かすには、ただ「賞を取った」と書くだけでは不十分です。
「なぜ受賞できたのか」「その経験から何を学んだのか」を言葉にすることが大切です。
たとえば、次のように書くと、採用担当者の心に響きやすくなります。
| 良い自己PR例 | 解説 |
|---|---|
| 〇〇コンクールで優秀賞を受賞しました。作品作りでは、テーマを深く掘り下げ、自分の視点で表現することを意識しました。この経験を通して、物事を多角的に捉える力と粘り強さを身につけました。 | 結果だけでなく、プロセスと学びを伝えている。 |
| △△コンテストで優良賞を受賞しました。地道な準備を重ね、最後まであきらめずに仕上げた経験が、自分の強みになっています。 | 努力の過程を強調して誠実さをアピール。 |
このように、受賞の背景を説明すると、単なる「結果報告」ではなく「成長の証」として伝わります。
受賞経験を強みに変える方法
受賞経験を強みにするためには、その経験を“今にどう活かしているか”を伝えることがポイントです。
たとえば、「優秀賞を受賞した経験から、物事を妥協せずに仕上げる姿勢を持つようになった」といった具体的な変化を示すと説得力が増します。
また、面接などで話すときは、「受賞のために工夫した点」「難しかったこと」「それをどう乗り越えたか」をエピソードとして話すと効果的です。
企業は結果よりも、そこに至るまでのプロセスや考え方を重視しています。
優良賞や優秀賞は、その人の姿勢や努力を示すシンボルです。
自分の強みと結びつけて語ることで、評価をさらに高めることができます。
また、履歴書に書く際には、過去の出来事として終わらせるのではなく、「今もそれを活かしている」と伝えると印象が一段上がります。
たとえば「受賞経験を通して身につけた集中力を、現在の仕事にも活かしています」といった形です。
受賞はゴールではなく、未来につながるスタートとして捉えることが、最大の活用法です。
まとめ|優良賞と優秀賞の違い
| ポイント | 内容まとめ |
|---|---|
| 優良賞と優秀賞の基本的な意味 | 優良賞は「安定した完成度の高い作品」、優秀賞は「特に優れた作品」に贈られる。 |
| 評価基準の違い | 優良賞は基礎力とバランス、優秀賞は独創性と完成度が重視される。 |
| 順位の違いと扱われ方 | 一般的には「入選 → 優良賞 → 優秀賞 → 金賞」の順で評価が上がる。 |
| 優良賞を取るためのコツ | 丁寧さ、テーマ理解、バランスの良さを意識することがポイント。 |
| 優秀賞を目指すためのポイント | 独自性・完成度・伝わりやすさの3つを意識して制作する。 |
| 受賞経験を強みに変える方法 | 受賞の背景や学びを自己PRで語ることで、説得力が増す。 |
優良賞と優秀賞の違いは、単なる順位の差ではなく、評価されるポイントの違いにあります。
優良賞は誠実な努力と安定した成果、優秀賞は高い完成度と独創的な発想が評価されます。
どちらも立派な成果であり、受賞は努力の証として胸を張って良いことです。
また、履歴書や面接でのアピールにもつなげることで、経験を未来の成長に活かすことができます。
受賞を「終わり」ではなく「次の挑戦のスタート」として捉え、自分の可能性をさらに広げていきましょう。