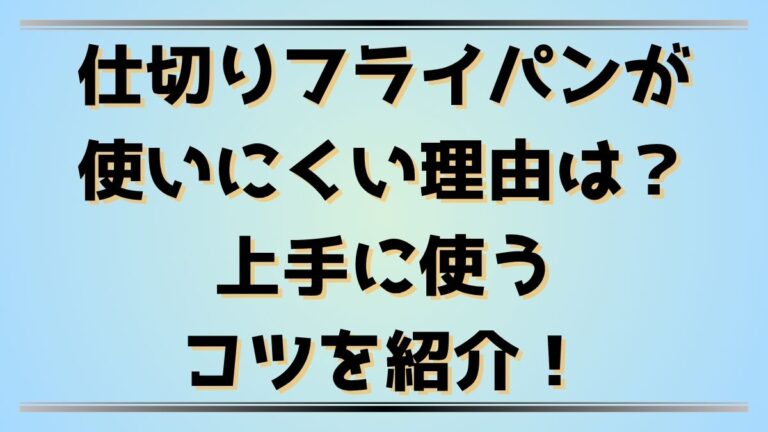仕切りフライパンが使いにくいと感じていませんか。
一度に複数の料理を作れる便利な調理器具として人気の仕切りフライパンですが、「火が均一に通らない」「洗いにくい」「収納しづらい」など、実際に使ってみると不便さを感じる人も少なくありません。
しかし、選び方や使い方を少し工夫するだけで、仕切りフライパンは驚くほど使いやすくなります。
この記事では、仕切りフライパンが使いにくいと言われる理由と、その改善方法、そして上手に活用するためのポイントを詳しく解説します。
読んだあとには、「なるほど、こうすれば良かったのか」と思えるはずです。
仕切りフライパンをもっと便利に使いたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
仕切りフライパンが使いにくいと言われる理由

仕切りフライパンが使いにくいと言われる理由について解説します。
それでは、仕切りフライパンが使いにくいと感じる理由を順番に見ていきましょう。
火の通りが均一にならない
仕切りフライパンの最大のデメリットとしてよく挙げられるのが、火の通りが均一にならない点です。
仕切りがあることで熱の伝わり方が部分的に異なり、特定のエリアだけ焦げやすくなったり、逆に生焼けになったりすることがあります。
特にガス火の場合、中央の火力が強くなるため、外側の仕切り部分の食材が加熱不足になるケースも少なくありません。
また、素材によっても熱伝導率が異なるため、アルミ製の仕切りフライパンでは比較的均一に加熱できますが、鉄製だと温度ムラが出やすい傾向があります。
このような場合は中火以下の安定した火力でじっくり加熱したり、フライパンを時々回すようにして調理することで、加熱ムラを防ぐことができます。
仕切りが邪魔で調理しづらい
仕切りフライパンは便利なようで、実際に使うと仕切りが邪魔になる場面が多いです。
特に炒め物や混ぜ合わせが必要な料理では、仕切りが壁のように動きを制限してしまいます。
また、卵焼きなどを作る際には、フライパンを傾けて形を整える動作がしづらくなるため、調理がスムーズにいきません。
こうした不便さを感じる人は多く、仕切りの高さが高いモデルほど、調理スペースが狭く感じられます。
一方で、仕切りの高さが低めのタイプを選べば、食材を動かしやすくなるため、多少の調理のしづらさは解消されます。
洗いにくくて手間がかかる
洗いにくさも仕切りフライパンの大きな欠点のひとつです。
仕切りの角や隙間に汚れや油が溜まりやすく、普通のスポンジでは届かない場所が出てしまいます。
その結果、食材のカスが残りやすく、時間が経つと焦げ付きやニオイの原因になります。
対策としては、細長いブラシやスポンジを使うのが効果的です。
また、フッ素加工やセラミック加工のタイプを選ぶことで、汚れが落ちやすく、洗う時間を短縮できます。
サイズが大きく収納しづらい
仕切りフライパンは構造上、普通のフライパンよりも幅が広く、厚みがあります。
そのため、収納スペースが限られているキッチンでは、収まりが悪く感じることがあります。
また、他の調理器具と重ねてしまうと、仕切りの部分に傷がついたり、コーティングが剥がれるリスクもあります。
最近では、取っ手が外せるタイプや立てて収納できるタイプも増えているので、収納性を重視する場合はそうしたモデルを選ぶのが賢明です。
収納スタンドを活用して立てると、スペースも有効活用できます。
重くて扱いにくい
仕切りフライパンは構造的に素材が厚くなりがちで、その分重くなる傾向があります。
特に3仕切り以上のモデルでは、食材を入れた状態で持ち上げるとかなりの重量になります。
重さによって片手で持ちづらく、洗う際にも手が滑りやすいという声もあります。
もし軽さを重視するなら、アルミ合金製や取っ手が軽いモデルを選ぶと扱いやすくなります。
また、調理の際は片方の手で取っ手を支えながら動かすことで、安定して調理ができます。
仕切りフライパンを上手に使うためのコツ

仕切りフライパンを上手に使うためのコツを紹介します。
それでは、仕切りフライパンを快適に使うための実践的なポイントを紹介していきます。
火加減を調整して加熱ムラを防ぐ
仕切りフライパンを上手に使うためには、火加減の調整がとても大切です。
仕切り部分によって熱の伝わり方が異なるため、強火で一気に加熱すると、部分的に焦げてしまうことがあります。
このような加熱ムラを防ぐには中火〜弱火でじっくりと温めるのがポイントです。
また、調理中にフライパンを少し回すようにして位置を変えると、全体に均等に熱が行き渡りやすくなります。
特にIHクッキングヒーターの場合は、均一加熱タイプの仕切りフライパンを選ぶと、火力のムラが出にくく快適に使えます。
仕切りを活かして同時調理をする
仕切りフライパンの一番の魅力は、異なる料理を同時に調理できることです。
しかし、仕切りを活かすには調理内容を工夫することが大切です。
例えば、一方の仕切りでは目玉焼きを焼き、もう一方ではソーセージや野菜を炒めるといったように、加熱時間の似ている食材を組み合わせるとスムーズに仕上がります。
また、仕切りごとに味付けを変えることで、同じ調理工程でもバリエーションのある料理を作ることができます。
このように、調理の組み合わせを工夫することで、仕切りフライパンの使いにくさを逆にメリットへと変えられます。
汚れが落ちやすいタイミングで洗う
仕切りフライパンは汚れが溜まりやすい構造をしているため、洗うタイミングが重要です。
調理後にすぐ洗うことで、油汚れや焦げ付きが固まる前に落とすことができます。
特に仕切りの隙間や角の部分は、スポンジが届きにくいため、温かいうちにお湯で洗うのが効果的です。
また、細長いブラシやシリコン製の細口スポンジを使えば、汚れをスッキリ落とすことができます。
フッ素加工やセラミック加工のタイプなら、少しの洗剤とぬるま湯で簡単に汚れを落とせるので、お手入れの手間も減ります。
取っ手が取れるタイプを活用する
仕切りフライパンを使いやすくするためには、取っ手が取れるタイプを選ぶのも一つのコツです。
取っ手を外せることで、洗いやすく、収納時も場所を取りません。
また、取っ手を外した状態でオーブンに入れることもできるモデルがあり、調理の幅がぐっと広がります。
特に、狭いキッチンや一人暮らしの方には、取っ手が外せるタイプが圧倒的に便利です。
収納面でもすっきり片付くため、仕切りフライパンをより快適に使えるようになります。
調理前に軽く油を塗って焦げ付きを防ぐ
仕切りフライパンを長くきれいに使うためには、焦げ付き防止の工夫も欠かせません。
調理前に、キッチンペーパーでフライパン全体に薄く油を塗ることで、焦げ付きにくくなります。
このひと手間で、食材が仕切りに張り付くのを防ぎ、洗いやすさも向上します。
また、フッ素加工やセラミック加工を傷つけないように、金属ヘラではなく木ベラやシリコンヘラを使用するのも大切です。
このように、焦げ付きを防ぐ工夫をすることで、仕切りフライパンの使い心地が格段に良くなります。
仕切りフライパンのメリット
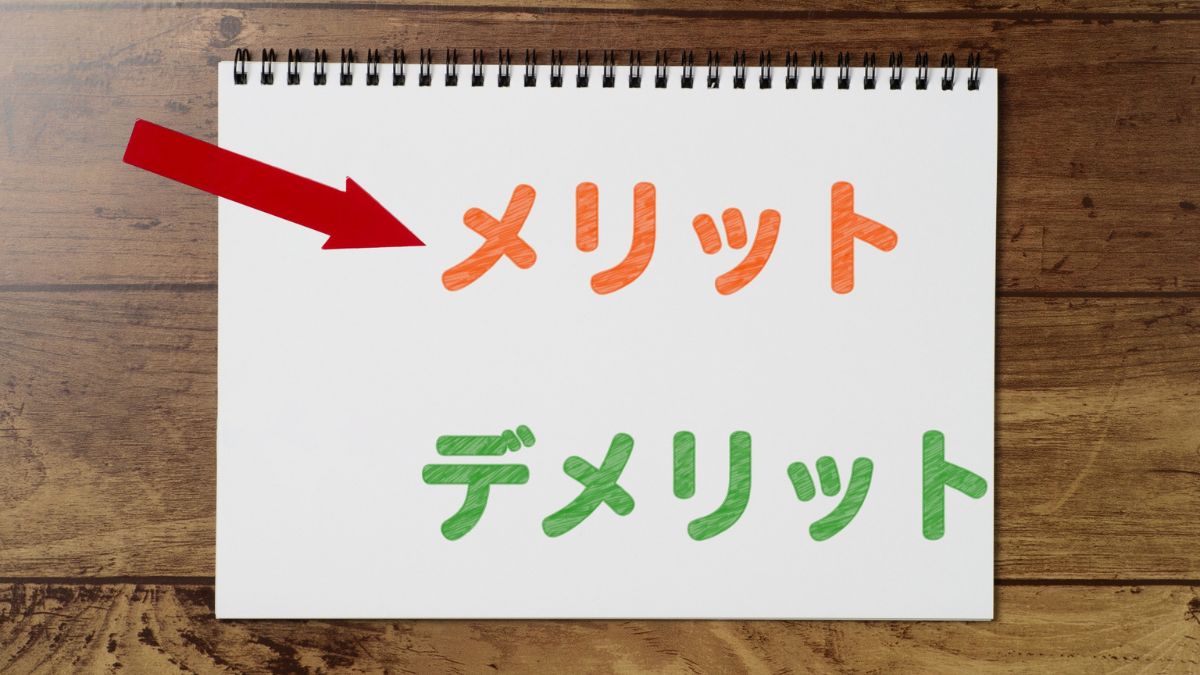
仕切りフライパンのメリットを知っておくことで、使いにくさを感じにくくなります。
それでは、仕切りフライパンを使うことで得られるメリットを一つずつ詳しく見ていきましょう。
一度に複数の料理が作れる
仕切りフライパンの最大のメリットは、複数の料理を同時に作れる点です。
仕切りがあることで、異なる食材を一つのフライパンで調理できるため、コンロが一口しかない環境でも効率的に調理できます。
例えば、片方で目玉焼きを焼きながら、もう一方でベーコンを焼いたり、野菜を炒めたりすることが可能です。
同時に火を通せることで調理時間が短縮され、忙しい朝の食卓やお弁当準備にも重宝します。
また、料理の温度管理もしやすく、焦げ付きや焼き過ぎを防ぐことにもつながります。
洗い物が少なくなる
仕切りフライパンは、洗い物の手間を大幅に減らしてくれます。
通常であれば、複数の料理を作る際に複数のフライパンや鍋を使う必要がありますが、仕切りフライパンなら一つで完結します。
そのため、調理後の片付けがとても楽になります。
一つのフライパンで済むというのは、特に一人暮らしや共働き家庭にとって大きなメリットです。
さらに、フッ素加工やセラミック加工のタイプを選べば、汚れが落ちやすく、時短効果がさらに高まります。
味が混ざらないで便利
仕切りがあることで、食材の味や香りが混ざらないのも魅力のひとつです。
例えば、魚と野菜を同時に調理しても、魚の匂いが他の料理に移ることがありません。
また、甘辛い味付けの料理と塩味の料理を同時に作っても、味が干渉しないので料理全体のバランスを保てます。
この特徴は、お弁当のおかず作りにも非常に便利で、見た目も整った料理が作れるようになります。
家族で好みが違う場合にも、仕切りごとに別の味を作れるため、無駄がありません。
忙しい朝に時短できる
仕切りフライパンは、時間を節約したい人にぴったりのアイテムです。
特に朝食やお弁当づくりでは、短時間で複数の料理を仕上げなければならないことが多いですよね。
そんなときに仕切りフライパンを使えば、同時に複数の食材を焼けるため、調理時間を大幅に短縮できます。
火を一度つけるだけで3品が同時に完成する効率の良さは、一度使うと手放せなくなる便利さです。
短時間で作りたいときほど、その効果を実感できる調理器具といえるでしょう。
お弁当づくりにぴったり
仕切りフライパンはお弁当のおかず作りに最適です。
お弁当用の小さなおかずをいくつも同時に作れるため、忙しい朝でも効率よく調理できます。
例えば、一つの仕切りで卵焼き、もう一つでウインナー、もう一つでほうれん草のソテーを作るなど、色合いのバランスも取りやすくなります。
また、それぞれの料理が混ざらないため、味が崩れず見た目もきれいなお弁当に仕上がります。
お弁当づくりを毎日続けている人にとっては、時短と仕上がりの美しさを両立できる頼もしい味方です。
仕切りフライパンの選び方
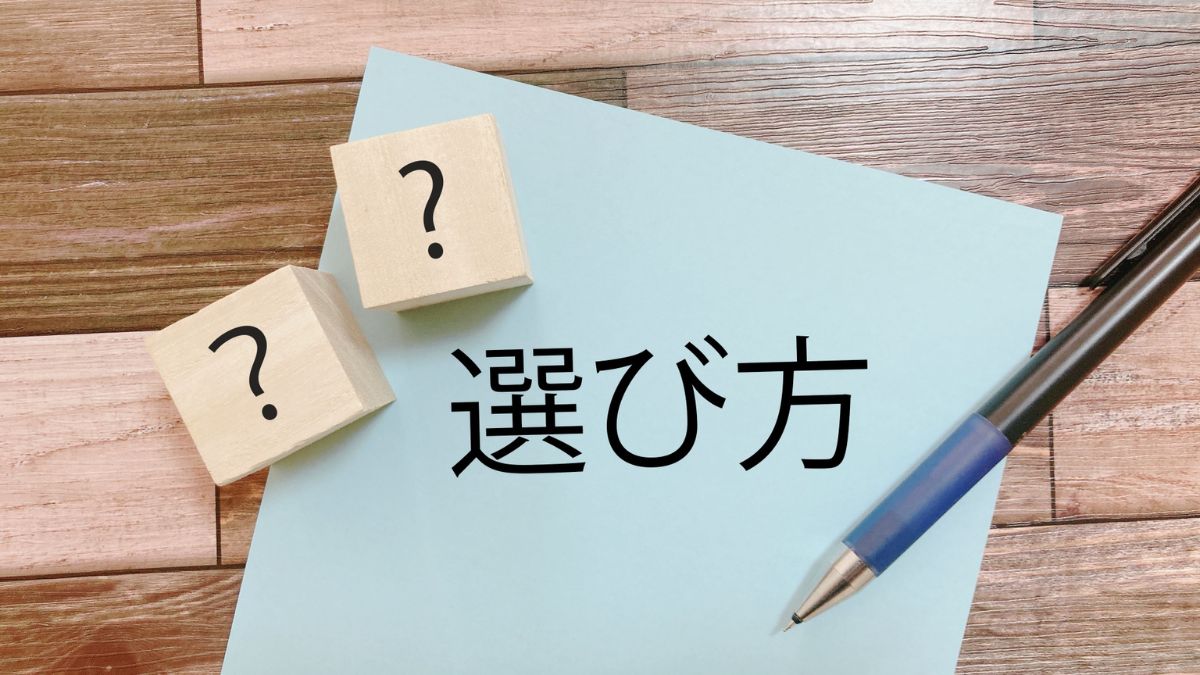
仕切りフライパンの選び方について詳しく紹介します。
それでは、自分に合った仕切りフライパンを選ぶために重要なポイントをひとつずつ解説していきます。
仕切りの数と形状をチェックする
仕切りフライパンを選ぶときは、まず仕切りの数と形状を確認することが大切です。
一般的には2〜3仕切りタイプが人気で、朝食やお弁当づくりに向いています。
一方で、4つ以上の仕切りタイプは多品目を同時に作れる反面、スペースが狭くなりやすく調理がしにくいという特徴もあります。
自分の調理スタイルに合わせて、仕切りの数を選ぶことが快適に使うポイントです。
また、形状にも「丸型」と「四角型」があり、丸型はパンケーキや目玉焼き向き、四角型は卵焼きやお弁当おかず作りに向いています。
素材とコーティングの違いを理解する
仕切りフライパンの使いやすさは、素材とコーティングの種類によって大きく変わります。
最も一般的なのはアルミ合金製で、軽くて熱伝導率が高く、扱いやすいのが特徴です。
鉄製は高温調理に向いており、ステーキや焼き魚など香ばしさを出したい料理に最適ですが、錆びやすいため手入れが必要です。
フッ素加工やセラミック加工などのコーティングは、焦げ付きにくく洗いやすいというメリットがあります。
特にフッ素加工タイプはコスパが良く、初心者にもおすすめです。
IH対応やガス火専用を確認する
仕切りフライパンを購入する前に、自宅のコンロに対応しているかを確認しましょう。
IHコンロを使用している場合、IH対応モデルを選ばないと加熱できません。
ガス火専用のものをIHで使用すると、うまく加熱できず、底が変形する恐れがあります。
最近ではIHとガス火の両方に対応したタイプも多く販売されているため、対応範囲の広いモデルを選ぶと安心です。
また、IH対応モデルは熱伝導のムラを防ぐ設計になっているものが多く、焦げ付きにくく使いやすい傾向があります。
取っ手の有無と収納性を比較する
仕切りフライパンはサイズが大きくなりやすいため、収納のしやすさも大切なポイントです。
取っ手が固定されたタイプは安定感があり、持ちやすい一方で、収納スペースを多く取ります。
反対に、取っ手が外せるタイプはコンパクトに収納でき、食洗機にも入れやすいのが特徴です。
キッチンが狭い場合や収納をすっきりさせたい人は、取っ手が取れるタイプを選ぶと使いやすいです。
また、立てて収納できるタイプや、吊るして保管できるモデルを選ぶとスペースを有効活用できます。
深さや重さを考慮して選ぶ
仕切りフライパンは深さと重さによって使い勝手が大きく変わります。
浅めのタイプ(約2cm前後)は目玉焼きやソーセージなどの焼き料理に向いています。
深めのタイプ(約4cm以上)は煮物や汁気のあるおかずにも対応できるため、より幅広い料理に使えます。
重さについては、アルミ製の軽量タイプを選ぶと片手でも扱いやすく、洗うときの負担も少なくなります。
また、厚みがあるフライパンほど保温性が高いので、料理を温かいまま食卓に出すのにも便利です。
まとめ|仕切りフライパンは工夫次第で使いやすくなる
| 使いにくいと感じる理由5つ |
|---|
| 火の通りが均一にならない |
| 仕切りが邪魔で調理しづらい |
| 洗いにくくて手間がかかる |
| サイズが大きく収納しづらい |
| 重くて扱いにくい |
仕切りフライパンは、確かに使いにくいと感じるポイントがいくつかあります。
しかし、火加減を工夫したり、仕切りの高さや素材を選んだりすることで、驚くほど快適に使えるようになります。
さらに、取っ手が外せるタイプやフッ素加工のモデルを選べば、収納やお手入れのストレスも減ります。
一度に複数の料理を作れるという時短と効率のメリットを活かせば、忙しい朝やお弁当づくりが格段にラクになります。
仕切りフライパンは、少しの工夫と選び方次第で「使いにくい道具」から「手放せない相棒」へと変わるアイテムです。
あなたの調理スタイルに合った一枚を選んで、毎日の料理をもっと楽しくしてみてくださいね。
参考リンク: