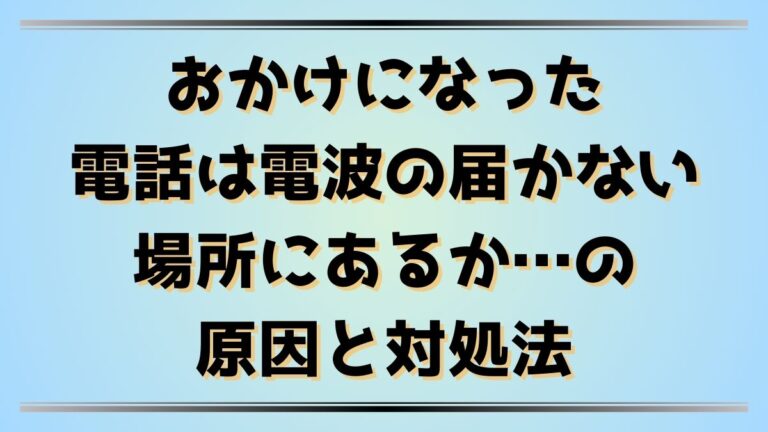「おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか」などのアナウンスが流れ、電話が繋がらないと不安になりますよね。特に、電源が入っているのにかからない、着信履歴が残らない、コールが鳴らず話し中になるなど、状況によって原因はさまざまです。
この記事では、ソフトバンク、ドコモ、au、UQモバイルなど各キャリアごとに考えられる原因とその対処法を解説します。
iPhoneやスマホの設定ミス、電波状況、通信障害など、見落としがちなポイントも徹底チェック。今すぐできる確認方法と改善策をまとめましたので、「どうすれば?」と困ったときにぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
-
「おかけになった電話は〜」というアナウンスの種類と意味
-
電話が繋がらない主な原因とその確認方法
-
通信会社ごとのトラブルの傾向と対策
-
発信・着信ができないときにまず試すべきこと
おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか|繋がらない主な原因

電話をかけたときに「電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません」といったアナウンスが流れると、どう対応すればいいか戸惑うものです。
実はこのようなケースには、いくつかの明確な原因があります。ここからは、電話が繋がらない主な理由について詳しく見ていきましょう。
電源が入っていない・バッテリー切れ
スマートフォンが圏外になる原因のひとつに、「電源が入っていない」または「バッテリー切れ」があります。
着信側の端末が完全に電源オフになっている場合、発信者側には「おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないため…」というアナウンスが流れます。
特にスマホはバッテリーの消耗が激しいため、こまめに充電していないと、知らない間に電源が落ちていることもあります。
また、機種によってはバッテリー残量が少なくなると自動的に電源が切れる設定になっている場合もあるため注意が必要です。
対策としては、まず相手のスマホの状態を確認する方法を考えること。
例えば、LINEやSNSで既読がつかない、返信が来ないなどのサインが見られる場合は、電源が入っていない可能性があります。
また、少し時間を置いて再度電話してみることで、電源が入れば着信できるようになります。
さらに、自分のスマホにも「電源が切れていないか」「バッテリーが極端に減っていないか」をこまめに確認する習慣をつけておくと、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
電波状況が悪い場所にいる
もう一つの代表的な原因が「電波状況の悪い場所にいる」ことです。
この場合も、「おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか…」というアナウンスが流れ、繋がりません。
例えば、地下鉄やビルの奥、山間部、または災害時などでは一時的に電波が不安定になることがあります。
また、家の中でも建物の構造によっては電波が届きにくい場所があり、特に鉄筋コンクリートの建物では圏外になることも珍しくありません。
さらに、通信キャリアの基地局のトラブルやメンテナンス、電波障害なども影響する場合があります。
こうしたケースでは、キャリアの公式サイトやTwitterアカウントで「通信障害情報」をチェックすることで、状況を把握できます。
一時的に繋がらない場合は、少し時間を空けて再度発信するのが基本ですが、LINEやメールなど他の手段も活用することで、相手に緊急性を伝えることができます。
また、どうしても電波が悪いと感じる場合は、Wi-Fi通話を有効にすることで屋内でもスムーズな通話ができる場合がありますので、設定の見直しも効果的です。
着信拒否や着信設定の問題
相手に電話が繋がらない場合、「着信拒否設定」や「おやすみモード」などの着信設定が原因となっていることがあります。
たとえば、特定の番号をブロックしていたり、知らない番号からの着信を拒否する設定が有効になっていたりすると、発信側には「おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか…」というアナウンスが流れることがあります。
また、スマートフォンの「おやすみモード」や「マナーモード中に着信を通知しない」といった設定がオンになっていると、実際には電波が届いていても相手からの呼び出し音が鳴らず、不在のように見えることがあります。
このような設定トラブルは、特に高齢者のスマートフォンや親が子どものスマホの利用を制限する目的で導入している場合によく見られます。
本人に悪気はなくても、知らず知らずのうちに設定が変わってしまっているケースもあります。
設定を見直す際は、スマホの「電話アプリ」や「設定」アプリ内で、「着信拒否リスト」「通知設定」などを確認してみましょう。
必要であれば、通話履歴を見て、相手からの着信が記録されていないかチェックすることも役立ちます。
通信会社のトラブル(docomo/au/ソフトバンク/UQモバイルなど)
携帯電話が繋がらないとき、個人の設定や端末の問題だけでなく、通信キャリア側のトラブルも視野に入れる必要があります。
たとえば、docomoやau、ソフトバンク、UQモバイルなどの通信会社で障害が発生すると、エリア一帯が通話不能になることがあります。
このような通信障害は、基地局のメンテナンスや災害時の設備損傷、またはシステム障害などによって引き起こされます。
特に大規模な障害時には、SNSやニュースサイトで大きく取り上げられることもあるため、まずは「通信障害」「〇〇(通信会社名) 障害」などのキーワードで検索してみると、リアルタイムで情報を得ることができます。
また、各通信会社の公式サイトやサポートページでは、現在の通信状況や障害発生エリア、復旧見込みなどを確認できる専用ページが用意されていることが多いです。
外出先やビジネスシーンで急な通話が必要な場合は、早めの情報確認がとても重要です。
なお、同じエリアで他の人の携帯電話も繋がらない場合、キャリアの問題である可能性が高いため、焦らず復旧を待ちつつ、LINE通話や固定電話などの代替手段を活用しましょう。
iPhoneやスマホの設定ミス
スマートフォンが繋がらない原因として意外と多いのが、「設定ミス」によるものです。特にiPhoneなどのスマートフォンは多機能であるがゆえに、何らかの設定が意図せず変更されてしまっているケースがあります。
たとえば、「機内モード」がオンになっていると完全に電波が遮断され、発信も着信もできなくなります。また、「通話の転送設定」が有効になっていて、他の番号に自動で転送されていることも原因となります。
iPhoneの場合は、「設定」→「モバイル通信」→「通信のオプション」や「キャリア」などをチェックしてみましょう。「キャリア設定のアップデート」がある場合、それが完了していないことで不具合が起きることもあります。
Androidの場合も同様に、機内モードや通話設定、アプリによる制限などが関係している可能性があります。特に節電アプリやセキュリティアプリが通話機能に制限をかけているケースもあるため注意が必要です。
スマホの設定を一つひとつ確認していくのは手間ですが、思わぬ部分が原因になっていることも多いので、通話トラブルが起きた際にはまず設定の見直しを行いましょう。
おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか|正しい対処法と確認ポイント

電話が繋がらない原因がわかったら、次に大切なのは適切な対処法を知ることです。何が原因で繋がらなかったのかを正しく見極めることで、より早く問題を解決できます。
ここでは、スマホやiPhoneの設定確認から、通信状況や回線のトラブル対応まで、効果的な確認ポイントと対策方法を紹介します。
まずは通話設定や端末状態を確認する
電話が繋がらないとき、「故障かな?」と思いがちですが、実はスマホ側の通話設定や端末状態の確認で解決できることが多くあります。
まず確認すべきは、「機内モード」「モバイルデータ通信」「VoLTE通話」などの設定です。これらの項目がオフになっていると、通話が正常に機能しません。特に再起動後やOSアップデート後は、設定が初期化されていることもあるため注意しましょう。
次に、端末自体の動作状況もチェックポイントです。動作が重くなっていたり、アプリが強制終了したりするようであれば、メモリ不足やOSの不具合が影響している可能性もあります。再起動やソフトウェアアップデートを試すことで改善されることがあります。
また、端末に装着されているSIMカードの接触不良も、通話機能に影響を与えることがあります。一度SIMを抜き差しして、しっかりと装着されているか確認してみるのも有効です。
通話できない場合は、こうした基本的な確認を一つひとつ丁寧に行うことが、原因を特定し早期に解決するための近道となります。
番号が現在使われているか検索・確認
電話が繋がらない原因のひとつとして、「相手の電話番号がすでに使われていない」可能性も考えられます。特に長期間連絡を取っていない相手に電話をかけた際や、名刺や古い連絡帳の情報を使って発信した場合に起こりやすいトラブルです。
このような場合、発信すると「おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないため…」という定型アナウンスが流れることがありますが、それ以外にも「この電話番号は現在使われておりません」という明確な案内がされることもあります。
確認方法としては、まず別の端末から同じ番号に発信してみること。これにより、機器や通信環境による問題か、番号そのものの問題かを切り分けることができます。また、通信会社によっては、ユーザーが番号を変更した際に旧番号にアナウンスを流すサービスも存在します。
ビジネスや緊急の連絡で相手に繋がらない場合、メールやSNSなど他の連絡手段を活用するのも一つの方法です。どうしても番号が有効かどうかを確認したい場合には、通信キャリアのサポートに問い合わせるという手段もあります。
基地局のトラブルや通信障害をチェック
携帯電話が通じないとき、その原因が通信会社側の「基地局トラブル」や「通信障害」であることも珍しくありません。基地局とは、各エリアでスマートフォンと通信を中継する重要な設備であり、これに不具合が生じると広範囲で電波障害が発生することがあります。
特に、台風や地震といった自然災害時には、基地局が一時的に停止するケースがあります。また、日常的にも設備メンテナンスやソフトウェア更新などで短時間の通信障害が起こることがあります。
基地局のトラブルが疑われる場合は、各通信キャリアの公式サイトやSNSで「障害情報」や「メンテナンス情報」を確認するのが効果的です。多くの場合、現在の障害エリアや復旧見込みが公表されています。
もし周囲の人も同じように通話ができない状況であれば、通信障害の可能性が高いため、無理にスマホを操作したり初期化したりする前に、情報収集を行うことが大切です。
代替手段としては、Wi-Fiを利用したLINE通話やビデオ通話、または固定電話の使用などが挙げられます。状況に応じて、柔軟に連絡手段を切り替える工夫が求められます。
固定電話や他端末からの発信で試す
スマートフォンからの発信で相手に繋がらない場合、まずは「自分側の問題なのか」「相手側の問題なのか」を切り分ける必要があります。その際に有効なのが、固定電話や別のスマートフォンなど他の端末から発信してみることです。
もし他の端末から発信した場合にスムーズに繋がるのであれば、自分の端末や契約中の通信キャリアに何らかの問題があると考えられます。一方で、他の端末からも繋がらない場合は、相手側の端末が電源オフまたは圏外である可能性が高まります。
また、固定電話からの発信であれば、スマホよりも安定した回線を使うことが多いため、より明確な判断ができることもあります。ビジネスなどでどうしても連絡が必要な相手には、この方法を試すことでトラブルを素早く解決することができます。
加えて、SIMカードの入れ替えが可能な場合は、別のSIMを試してみるのも一つの手です。自分の端末だけが繋がらない場合、SIMや設定の不具合が関係していることもあるためです。
「お呼びしましたがお出になりません」等のアナウンスの意味
電話をかけたときに流れるアナウンスには複数のパターンがあります。その中でもよく耳にする「お呼びしましたがお出になりません」というメッセージは、相手の端末には着信が届いているものの、応答がないという状態を表しています。
これはつまり、スマホの電源は入っており、通信状態も良好であるが、相手が電話に出ない・出られない状況にあるということです。たとえば、ポケットやバッグの中で着信に気づいていない、マナーモードで気づかない、あるいは会議中や運転中などが考えられます。
また、このアナウンスは「着信拒否」や「着信設定による拒否」が原因ではない点も重要です。あくまで物理的・状況的に出られないときに流れる案内であり、悪意や拒否を意味するものではありません。
ただし、同じアナウンスが何度か続く場合は、バッテリーが極端に少なく着信音が鳴らない、またはアプリの不具合などが原因となっていることもあります。そのため、緊急の場合はLINEやメッセージなど他の手段で連絡を試みるのも有効です。
このようなアナウンスの意味を正しく理解することで、不安や誤解を防ぎ、適切な対応につなげることができます。
まとめ
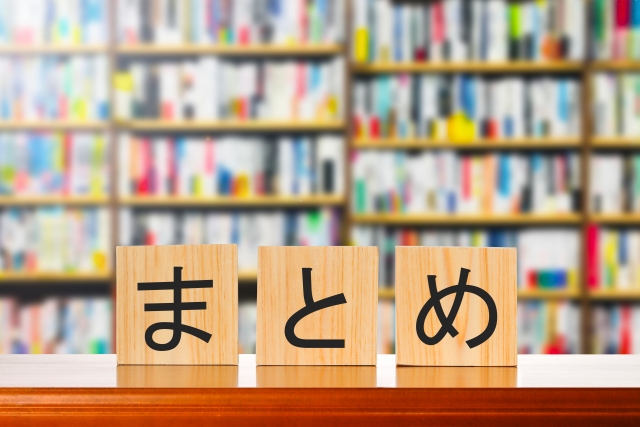
この記事のポイントをまとめます。
-
「おかけになった電話は〜」というアナウンスは、電源オフや圏外などが原因で流れる
-
スマホの電源が入っていない・バッテリー切れの可能性がある
-
電波状況が悪い場所にいると繋がりにくくなる
-
相手が着信拒否設定をしているケースもある
-
キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク・UQモバイル)の通信障害も原因の一つ
-
iPhoneやスマホの設定ミスで通話できない場合がある
-
通話設定や端末状態の確認が第一ステップ
-
利用中の電話番号が有効かどうかを検索で確認することも大切
-
基地局や通信設備のトラブルにも注意が必要
-
固定電話や別の端末での発信も試してみると原因切り分けに役立つ
電話が繋がらないと、不安や焦りを感じることが多いですが、原因を一つずつ丁寧に確認すれば、多くの場合は自分で解決可能です。電源の状態や設定、通信状況、キャリアの情報をチェックし、今回紹介した対処法を実践してみましょう。急ぎの連絡が必要な場面でも、冷静に対応できるようになるはずです。